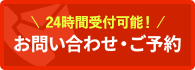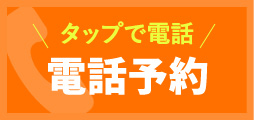頚椎症の手術は必要?判断基準・手術法・回復期間を専門家が徹底解説
2025/07/28 | カテゴリー:トピックス
【専門解説】頚椎症の手術は必要?適応の目安・手術方法・術後の注意点を徹底解説
頚椎症とは?手術が必要になるケースを理解する前に
**頚椎症(けいついしょう)**は、首の骨(頚椎)やその周囲の組織が加齢や姿勢の崩れにより変性し、神経や脊髄が圧迫されることで痛み・しびれ・筋力低下などの症状が出る疾患です。
主に以下の2つのタイプに分類されます:
-
頚椎症性神経根症:片側の肩・腕・手にしびれや痛みが出る
-
頚椎症性脊髄症:両手足のしびれ、歩行障害、排尿障害などが見られる
多くのケースでは保存療法(手術をしない治療)で十分対応可能ですが、一定以上に進行した場合は手術が必要になることもあります。
頚椎症で手術が必要になる症状と判断基準
保存療法では改善が見られないケース
通常、整骨院・接骨院での施術や病院での内服・リハビリなどの保存療法を3〜6ヶ月継続しても効果が乏しい場合、手術の選択肢が考慮されます。
特に以下の症状が長期にわたって続いている場合は要注意です。
-
しびれや痛みが日常生活に支障をきたすレベル
-
安静にしていても症状が続く、または悪化している
-
片手の握力や動きが著しく低下してきた
頚椎症性脊髄症と診断された場合
両手足にしびれがある/歩行障害が進行している/排尿・排便のコントロールが困難といった症状は、脊髄が圧迫されている状態であり、頚椎症性脊髄症が疑われます。
この場合、保存療法では回復が難しいため、手術によって神経圧迫を除去し、進行を防ぐことが重要です。
頚椎症の手術方法|目的と手技の違いをわかりやすく解説
頚椎症の手術は主に**神経の圧迫を取り除くこと(除圧術)**と、**不安定な骨や関節を固定すること(固定術)**を目的に行われます。
以下に代表的な術式をご紹介します。
1. 椎弓形成術(ついきゅうけいせいじゅつ)
後方からのアプローチで、椎弓という骨を一部削り、脊髄が通るスペースを広げる手術です。
-
脊髄の広範な圧迫に対応可能
-
骨を完全に切除せず「開いて固定」するので構造を温存しやすい
-
術後の可動域が保たれやすい
【適応】
-
頚椎症性脊髄症
-
多椎間にわたる圧迫
2. 前方除圧固定術(ACDF:前方頚椎除圧固定術)
前方(首の前側)からアプローチし、椎間板や骨棘を取り除いて神経の圧迫を解消します。
その後、人工骨などで骨を固定・癒合させます。
-
神経根や脊髄へのピンポイントな圧迫に有効
-
早期の改善が見込まれやすい
【適応】
-
椎間板ヘルニアや骨棘が原因の頚椎症
-
単椎間(1〜2箇所)の圧迫に限定される場合
3. ラミネクトミー(椎弓切除術)
椎弓形成術と似ていますが、こちらは椎弓を完全に切除して圧迫を取り除く術式です。
構造を大きく変更するため、術後に脊椎が不安定になるリスクもあるため、慎重に判断されます。
頚椎症の手術における入院期間・費用・保険適用について
入院期間の目安
-
一般的に7〜14日間の入院が必要
-
手術の方法や個人の回復力によって差あり
-
術後は1週間程度の安静→リハビリがスタート
費用と保険適用
-
保険診療の範囲内で3割負担の方で約15〜30万円程度
-
高額療養費制度の対象となるため、自己負担額の上限あり
-
入院時は差額ベッド代や食費などが別途必要
頚椎症の手術後に注意すべきこと
1. 術後すぐは首を安静に保つ
-
医師の指示によりネックカラーを装着することもある
-
車の運転・重い物の持ち運びは禁止(目安として術後1か月程度)
2. リハビリは必須
-
頚椎の可動域や筋力の回復を目的とした専門リハビリが必要
-
退院後もしばらくは通院が必要(週1〜2回)
-
肩こりや姿勢のクセを改善しないと再発の恐れあり
3. 術後のしびれはすぐに取れないことも
-
神経の回復には数か月〜1年程度かかることもある
-
しびれや違和感が残っても焦らず経過を観察することが大切
手術を回避したい場合の選択肢|まずは保存療法を見直す
手術に抵抗がある方、まだ保存療法での改善が見込める方は、原因に対する根本アプローチが重要です。
ふたば接骨院では以下の保存療法を重視しています:
-
姿勢の評価と修正
-
頚椎周囲の筋肉バランス調整
-
神経の通り道を広げるための整体施術
-
枕やデスク環境など生活習慣のアドバイス
-
セルフストレッチや体幹強化トレーニングの指導
手術に至らないようにするには、「症状の軽いうちに、根本原因にアプローチすること」が最も効果的です。
よくある質問(FAQ)|頚椎症の手術に関する不安を解消
Q1:手術をしてもしびれは完全に取れるの?
A:神経の回復には個人差があります。手術により圧迫が解除されても、すでに神経にダメージがある場合は完全には回復しないこともあります。
Q2:手術の後に再発することはある?
A:術部以外の椎間で新たに変性が起きれば、別の箇所で再発する可能性はあります。術後も姿勢や生活習慣の改善が大切です。
Q3:高齢でも手術は受けられるの?
A:全身状態や持病によって判断されますが、70代〜80代でも受けている方は多くいます。安全性を確認したうえで医師と相談しましょう。
Q4:リハビリはどのくらい続ければよい?
A:3か月〜6か月程度の継続が一般的です。症状や体力に合わせて徐々に再発予防メニューに切り替えていきます。
Q5:手術と接骨院の施術は併用できる?
A:術前術後の時期により異なりますが、術後リハビリ段階では接骨院でのサポートが非常に効果的です。
ふたば接骨院でも、術後リハビリや生活指導のサポートを行っています。
まとめ|頚椎症の手術は最終手段。正しい判断と準備が回復へのカギ
頚椎症に対する手術は、すべての患者さんに必要なわけではありません。
しかし、症状が進行して生活に支障がある場合、早期に適切な手術を受けることで改善が見込めるのも事実です。
手術を検討する前に大切なこと:
-
自分の症状が神経根症なのか脊髄症なのかを把握する
-
生活習慣や姿勢などの根本原因に向き合う
-
保存療法の取り組みを正しく行う
ふたば接骨院では、手術を避けたい方への保存療法の強化はもちろん、術後のリハビリサポートも対応しています。
「手術が必要かどうか不安」「保存療法でできることを知りたい」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
頚椎症の手術を受ける前にやっておくべき準備とは?
手術に臨む際には、身体面・生活面・精神面での準備がとても重要です。準備を怠ると、術後の回復が遅れたり、予想外の不安が生じたりすることがあります。
術前に必ず確認しておきたいポイント
1. 主治医との十分な相談
-
手術の目的(痛みを取るのか?神経圧迫を解除するのか?)
-
手術方法とその選定理由
-
合併症や後遺症のリスク
-
術後の回復プロセスと入院期間の想定
わからないことは何度でも確認し、不安をそのままにしないことが大切です。
2. 術後の生活に必要な準備
-
着替えや洗面など日常動作をサポートする道具の準備(マジックテープの服、ストロー、電動歯ブラシなど)
-
食料や生活用品の買い置き
-
家族や職場への休養期間の説明・調整
3. 体調管理
-
感染予防のため、風邪や口内炎の治療を事前に済ませておく
-
適度な運動と栄養で、術前の体力をキープ
頚椎症手術後の生活で気をつけるべきこと
手術後の回復を左右するのは、**術後の過ごし方にあります。**以下の点を意識して生活することで、合併症の予防や回復の促進につながります。
1. 術後直後の過ごし方(入院中)
-
まずは医師の指示に従って安静を保つことが基本
-
手術の種類によっては数日間、首のカラー(装具)を着用
-
排泄や移動にはスタッフのサポートを受け、無理に動かない
2. 退院後の生活の注意点
-
車の運転や自転車は医師の許可が出るまで厳禁
-
掃除機や洗濯など、体をねじる動作は控える
-
長時間のスマホ・読書など、うつむき姿勢の継続も避ける
3. 仕事復帰のタイミング
-
デスクワーク:術後2~4週間程度で復帰可能なことが多い
-
肉体労働:術後1か月以上の休養が必要になる場合もある
-
症状や仕事内容により異なるため、主治医の判断を仰ぐことが重要
手術後の再発を防ぐには?根本改善がカギ
せっかく手術を受けて改善しても、姿勢や生活習慣が変わらなければ再発のリスクがあります。以下の点を見直すことで、予防と健康維持につながります。
1. 正しい姿勢の維持
-
背筋を伸ばし、頭が肩の真上にある状態を意識
-
スマホ・PCは目線の高さに調整
-
長時間の同一姿勢を避け、30〜60分ごとに体を動かす
2. 寝具の見直し(枕・マットレス)
-
首の自然なカーブを保てる枕を選ぶ
-
柔らかすぎず、寝返りがしやすいマットレスを使用
-
うつ伏せ寝は避ける
3. 適度な運動とストレッチ
-
術後のリハビリが終了したら、自宅でも軽い体操やウォーキングを継続
-
首まわりの筋肉や肩甲骨の可動域を保つためのセルフストレッチも有効
手術を避けたい方へ|ふたば接骨院での保存療法とは?
ふたば接骨院では、「できるだけ手術はしたくない」「まだ症状は軽い」という方に向けた、非手術での根本改善プログラムを提供しています。
具体的なアプローチ内容
1. 姿勢と体のバランスの評価
-
頭の位置(前方偏位の有無)
-
骨盤・胸椎・肩甲骨の動きのチェック
-
神経の通り道の評価(整形外科的テスト)
2. 神経圧迫の緩和を目的とした整体施術
-
頚椎や胸椎の可動性を取り戻す施術
-
ストレッチと筋膜リリースによる筋緊張の緩和
-
肩甲骨〜胸郭の柔軟性を高めることで、首への負担を軽減
3. セルフケア・生活指導
-
ストレートネックや猫背対策のエクササイズ指導
-
枕の高さやPC作業時の環境指導
-
再発防止のための日常動作のコツや注意点もお伝え
患者さんから多く寄せられる「術後の不安」に答えます
Q:しびれが残ったままですが、手術は失敗ですか?
A:いいえ。**神経が長く圧迫されていた場合、回復に数か月〜年単位かかることもあります。**術後すぐに症状が消えないからといって失敗とは限りません。
Q:術後に運動やトレーニングはできますか?
A:術後1〜2か月の経過後に、主治医の許可が出れば可能です。
ただし、首に負担がかかるスポーツや高負荷トレーニングは避けるべきです。軽い体操やウォーキングから始め、徐々に強度を上げていきましょう。
Q:接骨院でリハビリを受けても大丈夫?
A:はい、**医師の指導に従いながら、安全な範囲で施術や運動を受けることは可能です。**ふたば接骨院では、術後リハビリにも対応しており、医療機関との連携も行っています。
まとめ|手術を受けるかどうかは「正しい情報と判断」が決め手
頚椎症で「手術」という言葉を聞くだけで不安になる方は少なくありません。
しかし、適切なタイミングで行えば生活の質を大きく改善できる手段でもあります。
そして、手術を回避したい場合も、早期から正しい保存療法に取り組むことで改善できるケースも多々あります。
ふたば接骨院では、以下のような方々をサポートしています:
-
「手術をすすめられたが、できるだけ回避したい」
-
「術後にリハビリや生活指導を受けたい」
-
「そもそも手術が必要なレベルか見極めたい」
お悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
適切な判断とサポートが、頚椎症の不安を大きく軽減します。