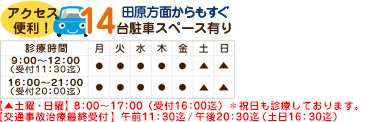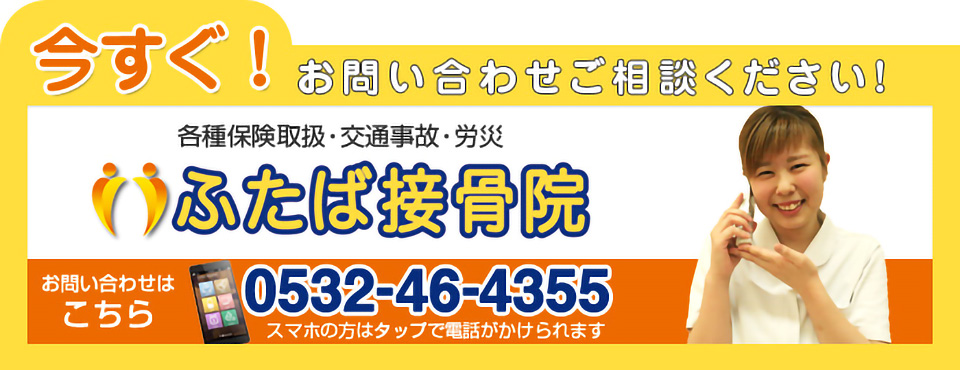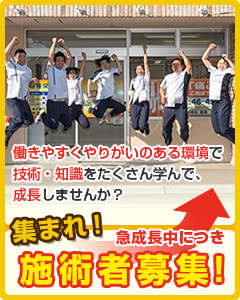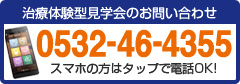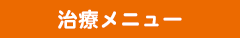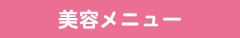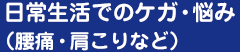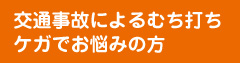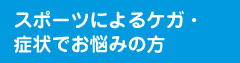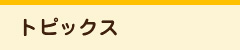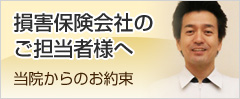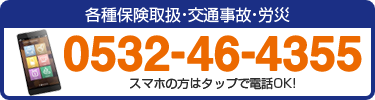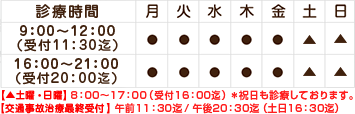【首こりと吐き気の関係】原因・対処法・整体での改善法を徹底解説
【首こりと吐き気】実は深くつながっている症状の関係性
なぜ首こりで吐き気が起こるのか?自律神経との関係
「首こりがつらいだけでなく、なぜか吐き気まで…」そんな症状に悩んでいる方は意外と多いです。この2つの症状、一見関係なさそうに見えますが、実は深くつながっているケースが少なくありません。
その背景には「自律神経の乱れ」が関係しています。首の周辺には交感神経と副交感神経が交差するポイントが多くあり、筋肉の緊張や血流の悪化によって自律神経が乱れると、胃腸の不調や吐き気が起こるのです。
また、首がこることで後頭部〜脳幹にかけての血流が滞り、脳の働きに影響を与えることで、めまいや吐き気、集中力の低下などの症状が出ることもあります。
首こりが原因の吐き気に見られる特徴とは?
首こりが原因で起こる吐き気には、いくつかの特徴的なパターンがあります。
このような症状がある場合は、内臓よりも「首まわりの筋肉や神経の過緊張」が原因かもしれません。とくにストレートネックや猫背といった姿勢の崩れがある方は、首に過度な負担がかかっている可能性が高くなります。
肩こりやめまいも併発?悪化する前に知るべきこと
首こりによって自律神経が乱れると、吐き気だけでなく「めまい」や「動悸」「手のしびれ」などの症状が一緒に出てくることがあります。これは、首周辺の筋肉の緊張が血流や神経の伝達を阻害してしまうためです。
このような状態を放っておくと、慢性化し、体調全体に影響を及ぼすようになっていきます。さらに症状が長引くことで、不安感やうつ症状を引き起こすケースも報告されています。
「なんとなく不調が続いている…」「病院では異常なしと言われたけどつらい」
そんな方は、首こりからくる自律神経の不調を疑ってみることをおすすめします。
あなたの症状は大丈夫?病院では異常なしと言われた方へ
病院で原因不明と言われた吐き気と首こりの関係
内科や脳神経外科を受診しても、「特に異常はありません」と言われてしまう…。しかし、症状は確かに存在し、生活に支障が出ている。このような方が多く来院されます。
実は、こうしたケースでは筋肉や骨格、神経のバランスの崩れによって自律神経が影響を受けている可能性が高いのです。病院で異常がないと判断されても、整体的な観点から見ると原因が明確になることがあります。
「どこに行っても原因がわからない」という方こそ、整骨院での体の状態チェックをおすすめします。
ストレートネックや猫背が関係しているケースとは?
現代人の多くが抱える「ストレートネック」や「猫背」は、首への負担を増大させる原因です。これらの姿勢不良によって、首の筋肉が過度に緊張し、血流が悪化しやすくなります。
とくにストレートネックは、首の自然な湾曲が失われているため、頭の重さがダイレクトに首や肩にかかる状態になり、慢性的な首こりやそれに伴う吐き気を引き起こします。
姿勢が悪くなることで、胸部の圧迫・呼吸の浅さ・自律神経の乱れも起こりやすくなります。こうした体の連鎖を断ち切るには、姿勢の改善と首まわりのバランス調整が不可欠です。
吐き気を伴う首こりが「危険な症状」のサインであることも
まれにですが、脳血管障害や頚椎の疾患が原因で、首こりと吐き気が同時に出ている場合もあります。以下のような症状がある場合は、まず医療機関の受診をおすすめします。
-
強い頭痛を伴う
-
手足のしびれ・感覚麻痺がある
-
吐き気が突然起こり、繰り返す
-
意識がもうろうとすることがある
これらの症状がある場合は、首こりとは別の要因の可能性があるため、整骨院ではなく病院での精密検査が必要です。
当院が行う首こり・吐き気の整体アプローチとは?
首のゆがみ・筋肉の過緊張がもたらす影響とは
当院に来院される方の中でも、「首のゆがみ」や「筋肉の過緊張」によって吐き気を伴う首こりが起きているケースは非常に多いです。
特に現代では、スマホやパソコンの長時間使用により、前傾姿勢が常態化している方が増えています。
そのような姿勢を続けることで、首の筋肉(特に後頭下筋群や胸鎖乳突筋)が固くなり、神経・血流の流れが悪化し、結果的に自律神経の不調や吐き気の症状へとつながっていきます。
当院では、こうした状態を的確に見極め、姿勢・筋肉・関節のバランスを整えていきます。
自律神経の乱れを整える整体アプローチ
首こりから来る吐き気を改善するには、「筋肉をほぐすだけのマッサージでは不十分」です。根本的には自律神経のバランスを整える施術が必要です。
当院では以下のようなアプローチを採用しています:
-
首〜背中の筋膜リリースで神経の通り道を解放
-
背骨・骨盤の歪み調整で全身の神経伝達を正常化
-
呼吸の深さを意識した自律神経安定の手技も導入
これにより、ただ首のコリを取るだけでなく、全身のバランスを回復させ、吐き気や不定愁訴の根本改善につなげていきます。
当院の施術と一般的なマッサージとの違い
「マッサージを受けたけど、またすぐ戻ってしまう」
そのような声をよく聞きます。
当院では一時的な緩和ではなく、体の根本原因にアプローチする施術を重視しています。
✅ 一般的なマッサージ
→ 筋肉表層を緩めるが、原因には届かない場合も多い
✅ 当院の施術
→ 姿勢・骨格・筋膜・神経の働きにアプローチし、全体を整える
また、初回にはしっかりとした検査を行い、吐き気の頻度や生活習慣のヒアリングを通して最適な施術計画をご提案いたします。
つらい吐き気を和らげる日常のセルフケア方法
簡単にできる首のストレッチ&姿勢リセット術
首こりによる吐き気を軽減するには、日常のケアもとても大切です。
以下のようなストレッチは、5分でできる簡単な方法としておすすめです。
これらのストレッチを1日2回ほど行うことで、首や肩の緊張を予防・緩和できます。
症状がつらいときは無理せず、痛みがない範囲で行ってください。
スマホ・デスクワークによる首の負担を減らす方法
吐き気を伴う首こりの多くは、長時間の前傾姿勢が原因になっています。
以下の工夫を取り入れることで、首への負担を大幅に軽減できます。
-
スマホは目線の高さで持つ
-
1時間に1回は立ち上がって伸びをする
-
椅子の背もたれにしっかりもたれて座る
-
顎を引いた姿勢を意識する
小さなことですが、こうした習慣の積み重ねが首の緊張を予防し、吐き気の発生頻度を減らすことにつながります。
睡眠・枕・食習慣から自律神経を整える生活習慣
自律神経の乱れによる吐き気を改善するためには、生活習慣の見直しも重要です。
特に意識したいのが以下の3つです。
-
睡眠の質を上げる
就寝前のスマホを控え、照明を暗めにして、深い睡眠を確保しましょう。
-
首に合った枕を使う
首の自然なカーブにフィットする枕を使うことで、睡眠中の首の負担を軽減できます。
※詳しくは「首こりと枕」の記事もご覧ください。
-
栄養バランスの取れた食事
ビタミンB群やマグネシウムは神経の働きを安定させるのに有効です。
整体施術と並行して、こうした生活習慣の改善を行うことで、症状の回復が早まるだけでなく、再発予防にもつながります。
首こり 吐き気に関するよくある質問
Q1. 吐き気のある首こりは整体で改善しますか?
はい、多くの方が整体によって症状の軽減や改善を実感されています。ただし、個人差がありますので、初回で丁寧にカウンセリングを行い、適切な施術を提案いたします。
Q2. 病院で異常なしと言われた場合も受診可能ですか?
もちろん可能です。むしろそのような方こそ、整体で体の歪みや緊張状態をチェックすることをおすすめします。原因不明の吐き気が、首こりから来ているケースは多くあります。
Q3. 自律神経が関係している場合の対応は?
当院では自律神経の調整を目的とした施術にも対応しております。首〜背中・骨盤を整えることで、神経系の働きを正常に導くアプローチを行っています。
Q4. 首こり以外にめまい・頭痛がある場合も対応できますか?
はい。めまいや頭痛も、首の緊張や自律神経の乱れから来ている可能性が高いため、併せて対応いたします。症状が複数ある場合も安心してご相談ください。
Q5. 通院の頻度はどれくらい必要ですか?
症状の強さによって異なりますが、最初は週1回程度から始めて、改善に応じて間隔を空けていくのが一般的です。目安は初回時に詳しくご案内いたします。
Q6. どのタイミングで整体に行くのがベスト?
首こりや吐き気を感じ始めた時点で、早めにご相談いただくのが理想です。初期段階での対処が、回復を早める鍵になります。
吐き気を伴う首こりにお悩みなら今すぐ当院にご相談ください
首こりと吐き気の関係は非常に深く、単なる筋肉の疲労ではなく、自律神経や全身のバランスの崩れが原因になっていることが多くあります。
「病院では異常がないけどつらい…」
「いつまでこの不調が続くのか不安…」
そんな方にこそ、当院の整体を受けていただきたいと思っています。
根本から体を整えることで、吐き気や首の不調を解消する道はあります。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご予約ください。初回カウンセリングでは、丁寧にお話を伺い、今のお身体の状態に最適な提案をさせていただきます。
整体に通うベストなタイミングと迷ったときの判断ポイント
「整体に行くのはちょっと大げさかも…」
「様子を見ていたらそのうち良くなるかもしれない…」
そんな風にお悩みの方も多いのではないでしょうか。
しかし、首こりや吐き気は我慢していても自然に回復しにくい症状です。とくに、自律神経が乱れている場合は、休養や睡眠だけでは回復が難しいケースもあります。
以下のような状態に心当たりがある方は、できるだけ早めの受診をおすすめします:
-
首のこりが1週間以上続いている
-
吐き気が日常生活に支障をきたしている
-
病院で異常なしと診断されたけど症状が改善しない
-
首こり以外にも頭痛やめまい、不眠がある
当院では、こうした症状に対して身体全体のバランスを整えるアプローチで、
一人ひとりに合わせた施術をご提案しています。
少しでも不調を感じたら、我慢せず、お気軽にご相談ください。「早めのケア」が、早期改善のカギです。
【首こり 枕】自分に合った枕が不調改善のカギ!
首こりと枕の関係とは?そのメカニズムを解説
日々の生活の中で「首こり」を感じている方は少なくありません。特に朝起きたときに首が痛い・重い・だるいといった症状がある場合、寝具、特に「枕」が関係しているケースが非常に多いです。首の構造は非常にデリケートで、頭の重さを支える筋肉や神経が集中しています。そのため、枕が合わないことで睡眠中にも負担がかかり、血流や神経の圧迫が首こりを引き起こすのです。
また、枕の高さや硬さが不適切だと、頚椎の自然なカーブ(生理的湾曲)が崩れ、首や肩に余計な負担がかかります。その結果、筋肉の緊張や血流不良が起こり、慢性的な首こりに発展してしまうのです。
より詳細な状態の確認やアドバイスをご希望の方は、当院までお気軽にご相談ください。
枕が原因で起こる首こりの特徴とは?
枕による首こりにはいくつかの特徴があります。例えば「朝起きたときに首や肩がだるい・痛い」「昼間より朝の方がつらい」といった症状がある方は、枕が合っていない可能性が高いです。これは、睡眠中の長時間にわたる不良姿勢によって、首や肩に過度のストレスがかかってしまっている証拠です。
また、枕によって頭の位置が高くなりすぎたり、逆に沈み込みすぎたりすると、気道が圧迫されていびきや呼吸の浅さにもつながります。結果として、眠りの質も低下し、疲労回復ができずに日中の首こりや肩こりがひどくなる悪循環に。
首こりを感じるタイミングや頻度を確認することで、枕の見直しが必要かどうかを判断できます。
首に負担をかける「NGな枕」の共通点
首こりを引き起こす原因となりやすいNGな枕にはいくつかの共通点があります。
-
高さが合っていない:枕が高すぎると首が前傾し、低すぎると後屈してしまい、首の自然な湾曲を崩してしまいます。
-
硬すぎる or 柔らかすぎる:硬い枕は圧力を分散できず、柔らかすぎると頭が沈み込みすぎて不安定になります。
-
形状が不自然:デザイン重視で首の形に合っていない枕も首こりを助長します。
また、使い古して変形した枕も、当初のサポート機能を失っており、首に余計な負担をかけている可能性があります。定期的な買い替えや見直しが大切です。
首こりに悩む人が知っておきたい「理想の枕」とは?
高さ・素材・形状…首にやさしい枕の選び方
理想的な枕を選ぶポイントは、「頭と首をバランスよく支えること」です。具体的には、仰向け時に首の後ろと枕の間に適度な支えがあり、自然なS字カーブを保てる高さが理想です。
また、素材にも注目しましょう。通気性の良い素材、体圧分散に優れたウレタンやパイプ素材などがおすすめです。形状に関しては、首元が少し高く、後頭部が安定する凹みのあるタイプが、首のラインにフィットしやすいとされています。
首こりが強い方は、寝返りがしやすいかどうかも選定基準に入れると良いでしょう。
首こりに合うおすすめの枕タイプ【整体師目線】
当院では首の構造や筋肉の働きに基づいて、以下のような枕をおすすめしています。
-
低反発ウレタン製枕:首の形に沿って沈み込み、負担を軽減。
-
首のくぼみにフィットするカーブ型枕:頚椎の湾曲を自然にサポート。
-
パイプ素材の高さ調節可能枕:使用者に合わせて細かく調整できる。
ただし、どれほど良い枕でも、使う人の体格・姿勢・筋肉の緊張状態によって合う合わないがあります。迷われた際は、当院でのご相談も可能です。
良い枕を使っても改善しない理由とは?
「良い枕に変えたのに、首こりが全然治らない…」と感じていませんか?
実は、首こりの原因が日常姿勢の歪みや筋肉の過緊張にある場合、枕だけでは不十分なケースが多いです。
とくに、スマホの長時間使用やデスクワークによって、ストレートネックになっている方は、どんなに高機能な枕を使っても根本解決にはつながりません。
まずは、整体などで首の歪みや筋肉の状態を整えた上で、適切な枕を選ぶことが最も効果的です。
当院の整体施術で枕だけでは解消できない首こりを根本改善!
首こりを放置するとどうなる?代表的なリスク3選
「たかが首こり」と軽く見ていると、身体全体にさまざまな不調が波及するリスクがあります。主なリスクは以下の3つです。
-
頭痛・めまい・吐き気:首の筋肉の緊張が血管や神経を圧迫し、脳への血流不足や自律神経の乱れを引き起こします。
-
肩こり・背中の痛みの悪化:首の不調は連鎖的に肩・背中・腰へと波及し、慢性化する恐れがあります。
-
睡眠の質の低下:寝付きにくさや浅い眠りにつながり、回復力が低下してさらなる体調不良へ。
このように、首こりは放置すると慢性化しやすく、生活の質を大きく下げる原因になります。早めの対処が重要です。
整骨院でできる首こりケアとセルフケアの違い
セルフケアで首こりが楽になることもありますが、一時的な改善にとどまるケースが多いです。一方で整骨院では、以下のようなアプローチが可能です。
当院では、日常生活における癖や姿勢のチェック、首や肩の可動域の検査を通して、原因を特定し、個々に合わせた施術を行っています。
当院の首こり施術の特徴と改善事例
当院では、首こりに対して以下のようなアプローチで施術を行っています。
-
頚椎の調整・骨盤との連動性を重視した整体
-
筋膜リリースや手技療法を組み合わせたアプローチ
-
猫背矯正や姿勢指導による再発防止策の提案
また、首こりだけでなく、「眠りが浅い」「肩がいつも重だるい」などの悩みを持つ方にも対応しています。施術後は視界がクリアになった、頭痛が軽くなったと感じる方が多いのも特徴です。
施術内容の詳細については、当院の公式ページ(こちら)をご覧ください。
首こりの改善と予防に効く!おすすめセルフケア習慣
寝る前にできるストレッチで首こり予防
首こりは、寝る前のわずかなストレッチでも予防や軽減につながります。おすすめは以下のような簡単な動きです。
-
首を前後左右にゆっくり倒すストレッチ
-
肩甲骨を寄せる動きで姿勢改善を意識
-
温かいタオルで首を温めながら深呼吸
ポイントは、無理のない範囲でリラックスした状態で行うこと。継続することで、筋肉の緊張を緩め、より良い睡眠と快適な目覚めにつながります。
日中の姿勢改善が枕選びよりも重要な理由
いくら良い枕を使っても、日中の姿勢が悪ければ首こりの根本解決はできません。とくに多いのが、以下のような悪習慣です。
-
スマホを長時間下向きで見る「スマホ首」
-
デスクワーク中の猫背・前のめり姿勢
-
片側に重心をかけた立ち姿勢
これらが続くと、首の筋肉や関節に大きなストレスがかかり、睡眠時の枕だけではカバーしきれない負担がかかります。
当院では、姿勢チェックや生活動作の改善指導も行っておりますので、根本から改善したい方はぜひご相談ください。
枕だけじゃない!首に優しい睡眠環境の整え方
首こり対策には、枕だけでなく「寝具全体」や「室内環境」も重要です。以下のポイントを見直してみましょう。
-
マットレスや敷布団の硬さ・沈み具合:柔らかすぎる寝具は体が沈みこみ、首に負担が集中します。
-
室温・湿度の調整:寒すぎる環境は筋肉の緊張を高める原因に。
-
寝る前の光・音の刺激を減らす:睡眠の質を高め、回復力を促進します。
これらを整えることで、枕の効果を最大限に引き出し、首への負担をトータルで減らすことが可能になります。
首こり 枕に関するよくある質問
Q1. 首こりがひどくて枕が合わないのですがどうすれば?
まずは現在の首の状態をチェックすることが重要です。筋肉の緊張や頚椎の歪みがある状態で枕を変えても効果が出にくいことがあります。一度、整体などで身体を整えてから枕を見直すと、合う枕が見つかりやすくなります。
Q2. 首こりにおすすめの枕の高さは?
一般的には、仰向けで首とマットレスの間に指1~2本分の隙間ができる高さが理想とされています。個人の体格や寝姿勢によって最適な高さは異なりますので、微調整が可能な枕を選ぶのがベストです。
Q3. 整体院で枕の相談はできますか?
はい、当院では施術時に枕の選び方や使い方についてのご相談も受け付けております。ご希望の方はカウンセリング時にお気軽にお伝えください。
Q4. 高反発と低反発、首こりに良いのはどっち?
どちらが良いかは人それぞれですが、首こりが強い方には適度なサポート力がある「中反発〜やや高反発」が合いやすい傾向があります。寝返りのしやすさや安定性を重視して選ぶと失敗が少ないです。
Q5. 整体を受けると枕が合いやすくなりますか?
はい、整体で首の歪みや筋肉の状態を整えると、枕とのフィット感が格段に上がります。枕の性能を最大限活かすためにも、まずは身体のバランスを整えることをおすすめします。
Q6. 市販の枕で改善するケースはありますか?
もちろんあります。最近では、調整機能が付いた枕や、首の湾曲に合わせた設計のものも増えています。ただし、選び方を間違えると逆効果になることもあるため、自分の首の状態に合ったものを選ぶようにしましょう。
つらい首こりでお悩みの方へ|今すぐ当院へご相談ください
首こりが続くと、生活の質の低下・慢性化・他の不調の原因にもつながります。枕の見直しはもちろん重要ですが、それだけでは不十分なケースも多くあります。
当院では、整体による根本的なアプローチ・姿勢の改善・日常生活へのアドバイスまで、トータルでの改善をサポートしております。
「朝起きたときに首がつらい」「枕を変えても良くならない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回カウンセリング・姿勢チェックも受付中です。お気軽にご予約ください。

こんにちはふたば接骨院・鍼灸院です。
朝晩がひんやりと感じられるようになり、秋の深まりを感じる季節となりました。
10月は気温の変化が激しく、身体の不調や疲れが出やすい時期でもあります。特に、骨盤のゆがみや姿勢の乱れがあると、季節の変わり目に体がついていかず、肩こり・腰痛・冷えなどを引き起こしやすくなります。
今回は、当院でも多くの方に支持されている「リバースボディ療法」と「骨盤矯正」について、詳しくご紹介いたします。
「最近なんとなく調子が悪い…」と感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
「骨盤のゆがみがもたらす不調とは?」
骨盤の役割と体への影響
骨盤は、体の中心に位置し、上半身と下半身をつなぐ非常に重要な役割を持つ部位です。骨盤の中には内臓を支える器官が収まっており、また脊椎と股関節の連結点として体のバランスを支えています。歩く、立つ、座るなど、日常のあらゆる動作に深く関係しており、骨盤が正しい位置にあることで私たちの身体はスムーズに動くことができます。
しかし、骨盤がゆがむことでその機能が正しく働かなくなり、筋肉のバランスが崩れたり、神経や血流の流れが滞ったりすることがあります。これが、慢性的な肩こりや腰痛、疲労感、姿勢の悪化など、全身の不調につながってしまうのです。
骨盤がゆがむ原因とは
骨盤のゆがみにはいくつかの原因がありますが、代表的なものとして以下のようなものが挙げられます。
このような日常の何気ない習慣が積み重なることで、骨盤は少しずつズレを起こしてしまいます。そして、このズレが慢性化すると、腰痛や股関節の痛みなどの明確な症状として現れてくるのです。
ゆがんだ骨盤が引き起こす具体的な症状
骨盤がゆがむことで起こる症状は多岐にわたります。以下は代表的な例です。
-
・腰痛・ぎっくり腰
-
・肩こり・首こり
-
・冷え性やむくみ
-
・姿勢の悪化(猫背・反り腰)
-
・下半身太り
-
・生理不順やPMSの悪化
また、見た目にも左右差が出てくることがあり、「足の長さが違う」「スカートがくるくる回る」「靴のすり減り方が違う」など、鏡を見たときの違和感に気づくこともあります。これらの症状は、骨盤が正しい位置に戻ることで徐々に改善されることが多いため、根本的な原因を見逃さないことが大切です。
リバースボディ療法の基本的なアプローチ
リバースボディ療法とは、身体のバランスを根本から整えることを目的とした整体手法のひとつで、特に骨盤や背骨のゆがみに着目してアプローチを行います。
一般的なマッサージや一時的な痛みの緩和を目的とした施術とは異なり、自律神経の調整や筋肉・関節の機能回復を通じて、身体が本来持つ「治ろうとする力=自然治癒力」を引き出すことを重視しています。
この療法では、過剰に力を加えることはせず、やさしく正確な手技で、筋膜や筋肉の緊張を緩めながら、関節の可動性を取り戻していきます。そのため、「バキバキ鳴らす矯正はちょっと怖い…」という方でも安心して受けていただけます。
従来の施術法との違い
リバースボディ療法の最大の特徴は、症状の出ている部分だけに注目しないという点です。
例えば、腰が痛いからといって腰だけを施術するのではなく、骨盤の傾き、脚の長さの差、背中や首の歪みなどを細かくチェックし、全身のバランスを整えながら、結果として症状の改善を目指します。
また、施術前後で姿勢の変化や可動域の改善を確認し、身体の状態を数値や感覚でしっかりと把握しながら進めていく点もリバースボディ療法の魅力です。単に「気持ちいい」では終わらず、「どう変わったのか」を体感できるため、多くの患者様から信頼されています。
リバースボディ療法で期待できる効果
リバースボディ療法を受けることで、次のような効果が期待できます。
当院では、このリバースボディ療法を通じて、ただ痛みを取るのではなく、「根本改善」と「再発予防」に重きを置いた施術を提供しています。
「ずっと悩んでいた不調が、実は骨盤のゆがみから来ていたなんて…」と驚かれる方も少なくありません。
少しでも興味を持たれた方は、ぜひ一度当院までご相談ください。あなたの身体の状態を丁寧に確認し、最適な施術プランをご提案いたします。
「当院の骨盤矯正×リバースボディ療法の施術内容」
施術の流れと特徴
当院では、骨盤矯正とリバースボディ療法を組み合わせることで、より高い効果と持続性を実現しています。単なる対症療法ではなく、「なぜ今その症状が出ているのか?」という根本的な原因を追究し、施術に活かしています。
施術の流れは以下の通りです。
-
1.カウンセリング・検査
初回はじっくり時間をかけて症状の背景をヒアリングし、骨盤の位置、足の長さの差、可動域などをチェックします。
-
2.リバースボディ療法による筋肉・関節の調整
全身のバランスを確認しながら、やさしい施術で筋肉の緊張を緩め、関節の可動域を広げていきます。
-
3.骨盤矯正
骨盤のゆがみを整えるための調整を行い、正しい位置にリセット。施術後には左右差や姿勢の変化を確認していただきます。
-
4.アフターケア・生活指導
再発を防ぐためのストレッチや日常生活のアドバイスを提供。施術効果の持続を目指します。
施術はボキボキと音を鳴らすような強い矯正ではなく、非常にソフトで心地よいものです。リラックスした状態で受けていただけるため、整体が初めてという方や高齢の方、妊娠中・産後の方でも安心して通っていただけます。
どんな方におすすめか
以下のような悩みをお持ちの方には、当院の施術が特におすすめです。
また、「整体は興味あるけど少し怖い」「マッサージではよくならなかった」という方にも、リバースボディ療法のやさしく根本にアプローチする手法は非常に好評です。
症状が出ていない方でも、「予防」として身体の状態をチェックし整えることで、将来的な不調のリスクを減らすことができます。
施術を受けたお客様の声
当院で実際に施術を受けられたお客様の声をご紹介します(※プライバシーに配慮し一部加工しています)。
30代女性/会社員:
「長年腰痛に悩まされてきましたが、こちらのリバースボディ療法と骨盤矯正を受けた後は、朝起きるのが楽になり、仕事中の腰の痛みも激減しました!先生がとても丁寧に説明してくれるので安心して受けられました。」
40代女性/主婦:
「産後の骨盤の開きが気になって受診。施術後、ズボンがスッと入るようになって驚きました。身体が軽くなり、気分も明るくなった気がします。」
50代男性/営業職:
「姿勢の悪さを指摘され続けてきたのですが、ここで施術を受けるようになってから、家族にも『背筋がピンとしたね』と言われるように。疲れも溜まりにくくなりました。」
このように、さまざまな年齢・ライフスタイルの方から高評価をいただいております。
気になる不調がある方は、ぜひ一度当院にてリバースボディ療法を体験してみてください。
「骨盤 リバースボディ療法に関するよくある質問」
施術は痛くないですか?
ご安心ください。当院のリバースボディ療法は、力任せに押したり、関節を強くひねったりすることは一切ありません。身体にやさしいソフトな手技で、筋肉や関節に無理なくアプローチします。
施術中に眠ってしまう方もいらっしゃるほど、リラックスできる施術です。整体や矯正が初めてで不安をお持ちの方でも、安心してお受けいただけます。痛みが強い部位や不安な点があれば、事前に丁寧にお伺いしながら進めてまいりますので、遠慮なくお知らせください。
何回くらい通えば効果が出ますか?
症状やお身体の状態によって個人差はありますが、初回の施術から「軽くなった」「姿勢が変わった」と体感される方が多いです。ただし、骨盤のゆがみや筋肉の緊張は長年の積み重ねによって起きているため、1回で完全に改善するわけではありません。
当院では、お客様一人ひとりの状態に合わせて、最適な施術ペース(週1回〜月2回程度)をご提案させていただいております。最終的にはメンテナンス通院(1か月に1回など)で再発を防ぎながら、良い状態をキープしていくことを目指します。
産後でも受けられますか?
はい、もちろん受けられます。むしろ産後こそ骨盤矯正が必要なタイミングです。出産により開いた骨盤は、正しいケアをしないと歪んだまま固まってしまい、腰痛・股関節痛・尿漏れ・体型の崩れなど、さまざまなトラブルの原因になります。
当院では、産後2か月頃から施術が可能です(帝王切開の方は傷の状態により応相談)。お子様連れでも安心して通えるよう、事前にご相談いただければ対応いたします。
保険は適用されますか?
リバースボディ療法および骨盤矯正は、自費施術(保険適用外)となります。これは、これらの施術が根本改善を目的とした整体施術であり、健康保険の適用範囲外となるためです。
ただし、交通事故後のむち打ち等で整骨院への通院が必要な場合は、保険適用のケースもございますので、該当の方はご相談ください。また、自費施術だからこそ、保険診療の枠にとらわれず、丁寧で自由度の高い施術をご提供できる点が強みです。
どのような服装で行けば良いですか?
施術当日は、動きやすい服装(ジャージ・スウェットなど)がおすすめです。ジーンズやスカート、体を締め付けるような服装、また金具やベルトが多い服は避けていただいた方が快適に施術を受けられます。
着替えを持参いただいても構いませんし、当院でお着替えのご用意もありますので、手ぶらでご来院いただいても大丈夫です。お仕事帰りや買い物の合間にも気軽にお立ち寄りください。
「骨盤のゆがみを根本改善!まずはお気軽にご相談ください」
骨盤のゆがみは、単なる姿勢の問題にとどまらず、肩こりや腰痛、疲労感、体型の崩れ、自律神経の乱れといった多くの不調の原因になります。
それを放置してしまうと、痛みや不快感が慢性化し、日常生活にも支障をきたしてしまうことも少なくありません。
当院では、やさしく丁寧なリバースボディ療法と、身体の土台を整える骨盤矯正を組み合わせることで、ただの一時的な緩和ではなく、根本改善と再発予防を実現します。
「ずっと悩んでいるけれど、どこに行けばいいか分からない」
「ボキボキ鳴らす矯正は怖い」
「薬や湿布に頼らない方法を探している」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当院の施術を体験してみてください。
初めての方にも安心してご来院いただけるよう、丁寧なカウンセリングと明確な説明を心がけています。あなたの身体の状態をしっかりと確認し、最適な施術プランをご提案いたします。
「もっと詳しく知りたい」「自分の不調に合っているか確認したい」という方は、
お気軽に当院までお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

◆交通事故のあと、「なんとなく腰が痛い」そんなお悩みはございませんか?
交通事故を経験された方の中には、「そのときは痛みがなかったのに、数日たってから腰に違和感が出てきた」とおっしゃる方が少なくありません。事故直後は、緊張や興奮状態のために痛みに気づかないことがあり、後になってじわじわと痛みや不調が現れるケースが多くございます。
「湿布を貼って様子を見ているけれど、なかなか改善しない」
「整形外科では骨に異常はないと言われたが、腰の痛みが取れない」
そのようなお悩みを抱えていらっしゃる方も多く、当院にもたくさんご相談をいただいております。
そこで、ぜひ知っていただきたいのが、当院の【リバースボディ療法】です。この施術では、腰痛の根本原因である骨格のゆがみや筋肉・神経の状態に対して丁寧にアプローチし、痛みの早期回復と再発予防を目指します。
また、交通事故が原因の症状に関しては「自賠責保険」が適用されるため、窓口でのご負担は原則として不要です。費用の心配なく、安心して専門的な施術を受けていただけます。保険に関するお手続きや書類のご相談も承っておりますので、初めての方でもご安心ください。
◆なぜ交通事故後に腰痛が起こるのでしょうか?
交通事故では、身体に強い衝撃が加わることで、筋肉や靭帯、骨格、神経などに目に見えないダメージが生じることがあります。とくに腰まわりは負担がかかりやすく、骨盤や背骨のゆがみにつながることも少なくありません。
レントゲンでは異常が見つからない場合でも、筋肉の緊張や神経の興奮、骨格のズレが原因となって、痛みが続いたり悪化したりするケースがございます。このような症状を放置してしまうと、慢性化して日常生活に支障をきたす可能性もありますので、早めの対応が大切です。
なお、交通事故後の治療については、整形外科と接骨院を併用して通っていただくことが可能です。
整形外科で診断や検査を受けながら、接骨院でリハビリや手技療法による回復サポートを受けることで、より効果的な治療が期待できます。
当院では、医療機関との連携や必要な書類のご案内も行っておりますので、安心してご相談くださいませ。
◆ふたば接骨院の「リバースボディ療法」で根本改善へ
当院では、交通事故による腰痛に対して、症状の一時的な緩和ではなく、**「根本からの改善」**を目指した治療を行っております。
●STEP1:骨格のゆがみを整える
交通事故の衝撃により、骨盤や背骨のゆがみが生じると、身体のバランスが崩れ、腰や背中への負担が大きくなります。こうした状態をそのままにしておくと、痛みが慢性化したり、日常生活に支障をきたすことにもつながりかねません。
当院では、身体の状態を丁寧に確認したうえで、骨格や筋肉、神経のバランスを整える施術を行い、根本からの回復をサポートいたします。
また、交通事故によるケガや不調については、「被害者の方」だけでなく、「加害者側の方」であっても通院が可能です。事故の状況にかかわらず、ご本人に不調がある場合は、早めに適切な処置を受けることが大切です。
任意保険に「人身傷害補償」が付帯されている場合、治療費が補償されるケースもございます。保険会社とのやり取りや必要書類についてもサポートいたしますので、ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
●STEP2:神経と筋肉の検査・治療
交通事故のあとに現れる痛みや不調は、見た目ではわからない筋肉や神経のトラブルが原因となっていることがあります。とくに腰まわりは衝撃を受けやすく、放っておくと慢性化してしまう可能性もございます。
当院では、丁寧なカウンセリングと検査をもとに、痛みの根本原因を見極め、お一人おひとりのお身体に合わせた施術を行っております。痛みの緩和だけでなく、再発しにくい身体づくりを目指してサポートいたします。
なお、交通事故の治療は、「被害者の方」だけでなく、「加害者側」の方でも通院していただくことが可能です。たとえ事故の加害者であっても、ご自身がケガをしている場合には、適切な治療を受けることが大切です。
任意保険に含まれる「人身傷害補償」によって、治療費の自己負担が発生しないケースもございます。保険の内容や申請手続きについても、丁寧にご案内いたしますので、ご不安なことがあればいつでもご相談くださいませ。
●STEP3:局所への治療(整体・鍼・電療)
当院では、交通事故によるお身体の不調に対して、患者さま一人ひとりの症状や状態に合わせた施術を行っております。整体や鍼灸、電気療法などを組み合わせることで、痛みの原因となっている部位に適切なアプローチを行い、早期の回復を目指します。
事故後の身体は外見上の異常がなくても、筋肉や関節、神経に目に見えないダメージを受けている場合が多くあります。そのまま放置すると、痛みが長引いたり、再発しやすくなったりする可能性もあるため、早めの対応が重要です。
なお、交通事故の治療は「被害者の方」はもちろん、「加害者側」の方でも通院が可能です。任意保険に人身傷害補償などが含まれている場合、ご自身の治療費も補償されるケースがあり、自己負担なく通院いただける場合もございます。
保険の内容や手続きについてのご相談にも対応しておりますので、事故後の身体に少しでも不安がある方は、どうぞ安心してご相談くださいませ。
●STEP4:インナーマッスルの強化
交通事故の衝撃により、身体の深部にある筋肉がうまく働かなくなり、姿勢のバランスが崩れたり、痛みが再発しやすくなることがあります。当院では、こうした深層筋(いわゆるインナーマッスル)に着目し、専用の機器や運動指導などを通じて、無理なく筋力を整えていくサポートを行っております。
筋肉のバランスが整うことで、身体全体の安定性が高まり、腰や肩、首などへの負担が軽減されるほか、今後の痛みや不調の予防にもつながります。
また、交通事故によるおケガの治療は、「被害者」の方だけでなく、「加害者側」の方も通院していただけます。たとえ加害者であっても、事故によって身体に不調が生じている場合は、早めの対応が重要です。
多くの場合、任意保険に含まれる「人身傷害補償」により、治療費の自己負担なく施術を受けていただけるケースがございます。保険の内容確認や書類の取り扱いについても丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。
◆リバースボディ療法の効果と実感
当院では、痛みの軽減を図るだけでなく、姿勢の改善や血流の促進、自律神経のバランスを整えることにも力を入れております。その結果、腰痛だけでなく、肩こりや全身のだるさなど、身体全体の不調が改善される方も多くいらっしゃいます。
「事故後、動くのもつらかったのに、通うたびに腰が軽くなっていくのを感じています」
「腰の痛みだけでなく、肩や首も楽になり、気分も前向きになりました」
といったお声を、患者さまから多数いただいております。
また、交通事故によるおケガの治療は、被害者の方はもちろん、加害者側の方も通院が可能です。たとえ事故を起こした側であっても、ご自身に痛みや不調がある場合は、適切なケアを受けることが大切です。
任意保険の内容によっては、治療費の自己負担なく通っていただける場合もございます。保険や手続きについても丁寧にご案内いたしますので、ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
◆交通事故治療には自賠責保険が適用できる場合もございます
交通事故によるおケガの治療については、自賠責保険が適用される場合、窓口でのご負担なく通院していただける可能性がございます。治療費の心配をせず、必要なケアに集中できるのは、大きな安心材料の一つです。
また、事故の加害者であったとしても、ご自身がケガをしている場合には治療を受けることができます。加害者の立場の方でも、任意保険に「人身傷害補償」などが含まれていれば、同様に自己負担なく治療を受けていただけるケースが多くあります。
当院では、事故後の身体の状態や不調に合わせた施術を行うとともに、保険会社とのやり取りや必要書類のご説明など、面倒に感じやすい保険手続きも丁寧にサポートしております。
「自分の場合は保険が使えるのか」「通院の手続きはどうすればよいのか」など、不安な点がございましたら、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせくださいませ。誠実に対応させていただきます。
早めの対応が未来の健康を守ります
交通事故のあとに感じる腰の痛みは、骨や関節の異常だけでなく、筋肉や神経といった身体の深部に原因があることも少なくありません。見た目では異常がなくても、不調が続く場合には、自己判断せず、専門家による適切な診察と施術を受けることがとても大切です。
当院では、事故後の体調や症状を丁寧に確認しながら、一人ひとりに合わせた施術を行っております。痛みの緩和はもちろん、再発しにくい身体づくりを目指して、日常生活を快適に送れるようサポートいたします。
また、交通事故が原因の症状については、「被害者」の方だけでなく、「加害者側」の方も通院いただくことが可能です。事故の状況にかかわらず、お身体に不調がある場合は、早めの対応が重要です。
任意保険の補償内容によっては、治療費が自己負担なく受けられる場合もございます。保険や通院に関するご不明点がございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。誠意をもって対応いたします。
交通事故によるおケガや後遺症は、放っておくと症状が長引いたり、日常生活に支障をきたすことがあります。今は大丈夫だと思っていても、時間が経ってから痛みや不調が現れることも少なくありません。だからこそ、早めのケアが大切です。
私たちは、患者さまお一人おひとりの身体の状態に合わせた丁寧な施術を行い、安心して日常を送っていただけるようサポートいたします。痛みの改善はもちろん、「また元気に過ごせる」という気持ちを取り戻していただくことを大切にしております。
また、交通事故の治療は被害者の方だけでなく、加害者側の方も通院していただけます。たとえ事故を起こした立場であっても、お身体に不調がある場合は治療を受ける権利があります。
任意保険に人身傷害補償が含まれていれば、治療費のご負担なく通えるケースもございます。保険に関するご相談も丁寧に対応いたしますので、どうぞ安心してお越しください。
ふたば接骨院と一緒に、笑顔と安心を取り戻す一歩を踏み出してみませんか?
詳しい治療内容はこちら
美容メニューもあります
交通事故のことならふたば接骨院へ
 頭痛薬に頼らない生活を矯正で目指す
頭痛薬に頼らない生活を矯正で目指す
ふたば接骨院では、初めてご来院いただいた際に、まず丁寧なカウンセリングと姿勢チェック、各種検査を行い、現在のお身体の状態や痛み・不調の原因を的確に把握いたします。
そのうえで、患者様一人ひとりに合わせた施術プランを立て、骨格矯正、筋肉へのアプローチ、神経の調整をバランス良く組み合わせた施術を行ってまいります。
特に、慢性的な頭痛の原因となる首や背中の歪みに対しては、正確な矯正施術を行うことで神経や血流の圧迫を和らげ、身体が本来持っている自然治癒力を引き出します。
また、施術による一時的な改善だけではなく、症状の再発を防ぐことも治療の大きな目的です。そのため、普段の姿勢のクセや生活習慣の中にある身体への負担を見直し、施術後には姿勢指導やセルフケアのアドバイスも丁寧にお伝えしております。
さらに、EMS(電気筋肉刺激)を活用したインナーマッスルのトレーニングによって、矯正後の骨格を安定した状態で維持できるようサポートします。正しい姿勢を支えるために必要な筋力を高め、歪みの再発を防ぐ効果が期待できます。
初回の施術時間は約60分ほどです。お身体の状態や生活スタイルに合わせた無理のない通院計画をご提案いたしますので、初めての方でもどうぞ安心してご相談ください。
【初めての方へ】ふたば接骨院の丁寧な矯正施術と通院プランのご案内
ふたば接骨院では、初めてご来院いただいた際に、まず丁寧なカウンセリングと姿勢のチェック、各種検査を通じて、現在のお身体の状態やお悩みの症状、痛みの原因を的確に把握いたします。
そのうえで、患者様一人ひとりに最適な施術プランを立て、骨格矯正、筋肉へのアプローチ、神経の調整をバランスよく組み合わせた施術を行ってまいります。
特に、慢性的な頭痛に深く関わる首や背中の骨格の歪みに対しては、正確で安全な矯正施術を行い、神経や血流の圧迫を緩和することで、身体が本来持っている自然治癒力を引き出します。
さらに、症状を一時的に和らげるだけでなく、再発を防ぐことも治療の大きな目的です。そのため、日常生活における姿勢のクセや体の使い方など、根本的な生活習慣の見直しにも注力しています。施術後には、姿勢改善のアドバイスやご自宅でできるセルフケア方法も丁寧にお伝えいたします。
また、矯正後の骨格を安定した状態で維持するために、EMS(電気筋肉刺激)を活用したインナーマッスルのトレーニングもご提案しています。正しい姿勢を支えるために必要な深層筋をしっかりと鍛えることで、歪みの再発を予防し、健康的な身体を維持しやすくなります。
初回の施術には、約60分のお時間をいただいております。お身体の状態やご都合に合わせた無理のない通院計画をご提案いたしますので、どうぞ安心してご来院ください。
ふたば接骨院の矯正施術と安心の通院サポート
ふたば接骨院では、初めてご来院いただいた際に、まず丁寧なカウンセリング、姿勢のチェック、各種検査を通じて、お身体の状態や症状の原因を的確に把握するところから始めます。
「どこが悪いのか分からない」「原因が特定できていないまま薬に頼っている」といった方にも、根本的な改善に向けた施術計画をご提案するための大切なステップです。
その上で、患者様お一人おひとりに合わせた最適な施術プランを立て、骨格矯正、筋肉へのアプローチ、神経の調整をバランスよく組み合わせた施術を行ってまいります。
特に、慢性的な頭痛に関係することが多い首や背中の歪みに対しては、正確かつ安全な矯正施術を実施し、神経や血流の圧迫を軽減することで、自然治癒力の向上と症状の緩和を目指します。
また、施術によって一時的に症状が軽くなるだけでなく、再発を予防することも当院の大きな目的です。そのため、施術後には日常生活における姿勢のクセや動作の見直しを丁寧にアドバイスし、ご自宅で行えるセルフケアや姿勢改善の方法もわかりやすくお伝えしています。
さらに、矯正で整えた骨格を安定させるためには、身体の奥にあるインナーマッスルの強化が不可欠です。当院では、**EMS(電気筋肉刺激)**を用いたトレーニングを取り入れ、無理なく深層筋を鍛え、歪みにくく疲れにくい身体づくりをサポートしています。
初回の施術には、しっかりと時間をかけて対応するため、約60分程度のお時間を頂戴しております。お身体の状態やご都合に合わせて、無理のない通院計画をご提案いたしますので、どなたでも安心してご相談ください。
頭痛改善へ導く整体施術のご案内
ふたば接骨院では、初めてご来院いただいた際に、まず丁寧なカウンセリングと姿勢チェック、各種検査を行い、お身体の状態や症状の原因を的確に把握いたします。
その上で、患者様一人ひとりに合わせた施術プランを立て、整体による骨格矯正、筋肉の調整、神経へのアプローチを組み合わせて、バランス良く施術を進めてまいります。
特に慢性的な頭痛に関わる首や背中の歪みに対しては、安全で効果的な整体施術を行い、神経や血流の圧迫を軽減します。
また、整体による改善後は、正しい姿勢の維持を目的に、生活習慣のアドバイスやセルフケア指導も行います。
さらに、整体で整えた骨格の安定を保つためにEMS(電気筋肉刺激)によるトレーニングもご提案しております。
初回は約60分のお時間を頂戴し、安心してご相談いただける環境を整えています。
矯正で整える頭痛改善整体プラン
ふたば接骨院では、初めてご来院いただいた際に、まず丁寧なカウンセリングと姿勢チェック、各種検査を通じて、お身体の状態や症状の原因を的確に把握いたします。
そのうえで、患者様一人ひとりの状態に合わせた施術プランを立て、整体による骨格矯正、筋肉の調整、神経へのアプローチを組み合わせて、全体のバランスを整える施術を行ってまいります。
特に、慢性的な頭痛に関わる首や背中の歪みに対しては、正確で安全な矯正施術を行い、神経や血流の圧迫を軽減することで、自然治癒力の向上と症状の改善が期待できます。
また、矯正後の効果を長く維持するためには、普段の姿勢や生活習慣の見直しが欠かせません。施術後には、日常生活における姿勢のクセや身体の使い方に対するアドバイス、ご自宅でできるセルフケアの方法も丁寧にご案内いたします。
さらに、矯正で整えた骨格を安定させるためには、インナーマッスルの強化が重要です。当院では、EMS(電気筋肉刺激)を用いたトレーニングをご提供しており、深層筋を効率よく鍛えることで、再び歪みが起こりにくい身体づくりをサポートしています。
初回の施術には約60分ほどのお時間を頂戴し、じっくりとお話を伺いながら施術を進めてまいります。矯正が初めての方でも安心して受けていただけるような環境づくりを心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
頭痛の根本改善へ導く整体施術
ふたば接骨院では、初めてご来院いただいた際に、まず丁寧なカウンセリングと姿勢チェック、各種検査を通じて、お身体の状態や症状の原因を的確に把握することからスタートいたします。
「どこが悪いのか分からない」「薬に頼るだけの対処では不安」とお悩みの方にも、根本改善を目指すための第一歩として、今のお身体の状態をしっかりとご説明いたします。
そのうえで、患者様一人ひとりに合わせた最適な施術プランを立て、整体による骨格矯正、筋肉への調整、神経のバランスを丁寧に整えながら、全身のバランスを整える施術を行ってまいります。
特に、慢性的な頭痛の原因となる首や背中の骨格の歪みに対しては、正確かつ安全な矯正施術を通じて神経や血流の圧迫を緩和し、身体が持つ自然治癒力を引き出すことを重視しています。
これにより、単なる一時的な緩和ではなく、再発しにくい状態をつくるための根本改善が期待できます。
さらに、施術後の生活習慣の見直しも根本改善の大切な要素です。姿勢のクセや日常的な身体の使い方について、アドバイスやご自宅でできるセルフケア方法をわかりやすくご案内し、より良い状態を維持できるようサポートいたします。
また、矯正で整えた骨格を安定させるために、インナーマッスルの強化も欠かせません。当院では、EMS(電気筋肉刺激)を活用したトレーニングを取り入れ、深層筋を効率よく鍛えることで、歪みにくく疲れにくい身体づくりを支えています。
初回の施術は約60分。しっかりお話を伺いながら施術を進めますので、根本改善を目指したい方にも安心して通っていただける環境を整えております。どうぞお気軽にご相談ください。
慢性的な頭痛を整体で根本改善へ導く方法
ふたば接骨院では、初めてご来院いただいた際に、まず丁寧なカウンセリングと姿勢のチェック、各種検査を行い、お身体の状態や現在の症状、そしてその根本的な原因を的確に把握するところからスタートいたします。
「どこが悪いのかわからない」「薬に頼るだけの対処では不安が残る」と感じている方も多いのではないでしょうか。当院では、そうした方々に対しても、根本改善を目指す第一歩として、身体の状態や不調の原因を丁寧にご説明し、ご理解いただいたうえで施術に進みます。
その上で、患者様お一人おひとりの体の状態や生活習慣に合わせた最適な施術プランを作成し、整体による骨格矯正、筋肉の調整、神経の調整を組み合わせたバランスの取れた施術を行ってまいります。
特に、慢性的な頭痛に深く関係することの多い首や背中の骨格の歪みに対しては、正確で安全性の高い整体施術を用いて神経や血流の圧迫を和らげ、身体本来の自然治癒力を高めることを重視しています。これにより、痛みの一時的な軽減にとどまらず、再発しにくい身体をつくるための根本改善が可能になります。
さらに、施術によって整った状態を維持するためには、日常生活での姿勢のクセや体の使い方の見直しが重要です。施術後には、セルフケアや姿勢改善のアドバイスも丁寧にご案内し、ご自宅でも継続的にケアできるようサポートいたします。
また、整体で整えた骨格を安定させるための重要なステップとして、インナーマッスル(深層筋)の強化も行っています。当院では、EMS(電気筋肉刺激)を活用したトレーニングにより、体幹を支える筋肉を効率的に鍛えることができます。これにより、歪みにくく疲れにくい身体づくりが実現し、より長期的な健康維持につながります。
初回の施術は約60分。しっかりとお話を伺いながら丁寧に進めてまいりますので、整体が初めての方も安心してご相談いただける環境を整えております。根本からの改善をお考えの方は、ぜひ一度ふたば接骨院へお越しください。
治療内容はこちら
予約方法はこちら
クーポンもございます

~矯正治療による根本改善のご提案~
はじめに:その頭痛、本当に「ただの疲れ」でしょうか?
「毎朝起きた瞬間から頭が重く感じる」
「仕事終わりの夕方になると決まってズキズキと痛み出す」
「頭痛薬を常備しないと不安で外出もできない」
このような慢性的な頭痛にお悩みではありませんか?
多くの方が「きっと疲れているだけ」「ストレスのせいかも」と思い込み、症状を我慢しながら生活を続けています。そして、その場しのぎとして市販の頭痛薬に頼りがちですが、実はそれが根本的な解決になっていないことも少なくありません。
実際には、頭痛の背景には首や肩、背中の筋肉の緊張や骨格の歪みが大きく関係している場合があります。特に現代社会では、長時間のスマートフォン操作やデスクワークによる悪い姿勢が慢性化し、知らないうちに身体に大きな負担がかかっているのです。
私たち「ふたば接骨院」では、そういった根本原因に着目し、**骨格矯正と神経・筋肉へのアプローチを組み合わせた「リバースボディ療法」**を導入しています。
ただ痛みを一時的に和らげるのではなく、再発しにくい身体づくりを目指した施術で、多くの患者様からご好評をいただいております。
慢性的な頭痛にお悩みの方は、ぜひ一度、当院の施術を体験してみてください。
頭痛の原因は、姿勢と骨格のゆがみにあるかもしれません
現代社会において、スマートフォンやパソコンの長時間使用は避けられないものとなっています。
その結果、多くの方が無意識のうちに前傾姿勢になり、**猫背やストレートネック(首が前に出る状態)**といった姿勢の崩れが慢性化しています。
このような姿勢の乱れは、首から肩、背中にかけての筋肉に常に負担をかけることになり、
・血流の悪化
・神経の圧迫
・筋肉の過緊張
といった身体の反応を引き起こします。その結果として、慢性的な頭痛や肩こりなど、日常生活に支障をきたす不調があらわれてしまうのです。
さらに、骨格の歪みがそのまま放置されてしまうと、身体全体のバランスが崩れ、自律神経の乱れや睡眠の質の低下、集中力の低下など、さまざまな不調へとつながる恐れがあります。
そこで重要になるのが、**姿勢や骨格の歪みに対する「矯正」**という視点です。
単なる対症療法ではなく、骨格を正しい位置に整えることで、根本からの改善を目指すことが可能になります。
当院のご提案:「リバースボディ療法」で根本から頭痛を改善
ふたば接骨院では、ただ痛みを一時的に取り除くだけでなく、再発を防ぎ、健康な身体を取り戻すことを目的とした施術を行っております。
① 骨格矯正(背骨・骨盤の調整)
ふたば接骨院では、身体への負担を最小限に抑えた専用の矯正ベッドを用いて、背骨や骨盤の歪みを安全かつ的確に整えていきます。
特に、頭痛の原因となりやすい**首の骨(頸椎)**の歪みを正しい位置へと戻すことで、首まわりの神経や血管の圧迫が軽減され、血流の改善や神経伝達の正常化につながります。これにより、慢性的な頭痛の症状が緩和されるケースも多く見受けられます。
当院で行う矯正施術は、「ボキボキ」と大きな音を鳴らすような強い矯正ではありません。お身体に優しいソフトな手法で、安全性を重視して行っておりますので、女性の方やご高齢の方でも安心して受けていただける内容となっております。
また、患者様お一人おひとりのお身体の状態や不調の原因を丁寧に見極めたうえで施術を行いますので、初めての方や矯正に不安をお持ちの方にもご好評をいただいております。
「無理なく、でもしっかりと」整える矯正で、頭痛の根本原因にアプローチしてみませんか?
② 神経の検査・治療(ハイボルト療法)
ふたば接骨院では、痛みの根本原因を正確に見極めるために、高電圧の電気刺激を用いた「ハイボルト検査」を導入しています。
この検査では、神経の伝達異常や筋肉の緊張といったトラブルが起きている部位を、表面的な症状にとらわれることなく、正確に特定することが可能です。
特に、
・痛みの原因となっている神経や筋肉
・反応が鈍く、動きが悪くなっている部位
をピンポイントで探し出し、的確なアプローチを行うことで、症状の改善が期待できます。
また、このハイボルト治療は即効性が高いことも大きな特徴で、初回の施術後から「痛みが和らいだ」「動かしやすくなった」と変化を実感される方も少なくありません。
さらに、骨格のバランスを整える矯正施術と併用することで、相乗効果が生まれ、より早い回復を目指すことができます。
ハイボルト検査で原因を明確にした上で、その根本にある骨格の歪みに対して矯正を行うことが、症状の再発防止にもつながるのです。
電気治療と矯正の組み合わせで、頭痛のない快適な日常を取り戻しましょう。
③ 筋肉・関節の修復(整体・鍼・特殊電気治療)
慢性的な頭痛を引き起こしている原因のひとつに、筋肉の過度な緊張や炎症、神経の圧迫が挙げられます。特に首や肩まわりの筋肉が硬くなってしまうと、その周辺の神経や血管が圧迫され、痛みや違和感を引き起こすことがあるのです。
ふたば接骨院では、こうした症状に対し、整体・鍼灸・特殊電気治療などを患者様の状態に応じて組み合わせ、身体の内側からの回復を促していきます。
整体では、筋肉や関節の可動域を広げ、血流やリンパの流れを整えることで、疲労物質の排出を助けます。鍼灸は、深部の筋肉やツボを的確に刺激し、自律神経の調整や炎症の抑制に効果的です。さらに、特殊電気治療によって患部への刺激を加え、細胞レベルでの修復を促進します。
このように、単一の施術だけでなく、多角的なアプローチを行うことで、頭痛の根本原因に対してより高い改善効果が期待できるのです。
「どの方法が自分に合っているのか分からない」という方でも、丁寧なカウンセリングをもとに最適な施術をご提案いたしますので、安心してご相談ください。
④ インナーマッスル強化(EMS)
正しい姿勢を長く維持していくためには、表面的な筋肉だけでなく、身体の奥深くにある「インナーマッスル(深層筋)」をしっかりと働かせることが重要です。
インナーマッスルは、背骨や骨盤などの骨格を支える役割を担っており、これが弱っていると、せっかく矯正によって整えた骨格もすぐに元の歪んだ状態へと戻ってしまいます。
そこで当院では、EMS(電気筋肉刺激)という機器を用いて、普段なかなか鍛えにくいインナーマッスルに直接アプローチを行います。
EMSによって筋肉が効率よく収縮・強化されるため、無理なく筋力アップが可能です。
このように、矯正によって骨格の位置を整えた後、EMSで筋力を強化することで、姿勢の安定性が増し、再び歪みが生じにくい身体へと導くことができます。
また、インナーマッスルの強化は、頭痛や肩こりなどの再発予防にもつながり、長期的な健康維持にも効果的です。
「その場だけの矯正ではなく、良い状態を維持したい」という方には、EMSと矯正の組み合わせを強くおすすめいたします。
実際にこのようなお悩みが改善されています
「10年以上も続いていた頭痛が、通院を始めてわずか3ヶ月で気にならなくなりました」
「薬を飲まなくても大丈夫な日が増え、毎日の生活が本当に楽になりました」
「姿勢を意識するようになってからは、見た目も変わり、自分に自信が持てるようになりました」
これらは、ふたば接骨院にご来院いただいた患者様から実際に寄せられたお声の一部です。
長年苦しんでいた症状でも、身体の状態を正確に把握し、段階を踏んで丁寧に治療を重ねていくことで、着実に改善が見られるケースが数多くあります。
特に「リバースボディ療法」による骨格矯正と神経・筋肉への多角的なアプローチは、頭痛のみにとどまらず、肩こり・めまい・不眠といった関連症状の軽減にも効果を発揮します。
当院では、その場しのぎではない「根本改善」を目指し、一人ひとりの症状や生活習慣に寄り添った施術をご提案しております。
慢性的な不調でお悩みの方は、どうぞ一度ご相談ください。私たちがしっかりとサポートいたします。
通院の流れと施術プラン
ふたば接骨院では、初めてのご来院時にまずカウンセリングや姿勢のチェック、各種検査を丁寧に行い、お身体の状態や症状の原因をしっかりと把握いたします。
その後、状態に応じて骨格矯正、筋肉へのアプローチ、神経の調整を組み合わせた施術を実施していきます。特に、頭痛の根本に関係する首や背中の歪みには、正しい矯正施術を行うことで、神経や血流の圧迫を解消し、自然治癒力を高める効果が期待できます。
また、症状の改善だけでなく再発を防ぐためには、日常生活での姿勢のクセや体の使い方を見直すことも重要です。そのため、施術後には生活習慣のアドバイスや、ご自宅でできる簡単なセルフケアの方法もご案内しております。
さらに、EMS(電気筋肉刺激)を活用してインナーマッスルを鍛え、矯正後の骨格の安定を維持するためのトレーニングもご提供しています。正しい姿勢を支える筋肉を強化することで、再び歪みが起こるのを予防します。
初回の施術には約60分ほどお時間を頂戴しております。お一人おひとりのお身体に合った、無理のない通院プランを丁寧にご提案いたしますので、初めての方も安心してご来院ください。
初めての方へ──安心してお試しいただくために
現在、初めての方に向けた**お得な初回限定クーポン(3,980円税込)**をご用意しています。
通常価格(8,800円税込)よりも大幅にお得なこの機会に、ぜひご自身のお身体の状態と向き合ってみませんか?
もう“仕方のない頭痛”とあきらめないでください
長年の頭痛に慣れてしまっていたり、薬に頼ることが当たり前になっている方にこそ、「矯正治療」を知っていただきたいと考えています。
骨格の歪みを整えることは、頭痛の改善だけでなく、身体全体のバランスを整えることにもつながります。
ふたば接骨院の「リバースボディ療法」で、頭痛の根本改善と、再発しない健康的な身体づくりを目指してみませんか?
一度お試しください
治療内容はこちら
ご予約はコチラから

頭痛がつらいあなたへ…その原因、実は“身体のゆがみ”かも?
頭痛の原因は脳じゃない!?見落としがちな「体のゆがみ」
病院で異常なし。それでも頭痛が続く理由
頭痛がつらくて病院を受診したけれど、「脳には異常ありません」と言われた経験はありませんか?
安心した反面、「でもこの頭痛は何なの…?」と不安が残る方も多いはずです。
実は、そんな“原因不明の頭痛”の背景には、身体のゆがみや姿勢の悪さが関係していることがよくあります。
現代人は長時間のデスクワークやスマホ操作などで、無意識のうちに猫背やストレートネックといった不良姿勢になりがち。
このような状態が続くと、首や肩周辺の筋肉が硬くなり、血流が悪くなります。
その結果、脳への酸素供給がスムーズに行われず、「なんとなく重い」「締め付けられるような」緊張型頭痛が起きやすくなるのです。
こうした状態には、薬ではなく整体による根本改善が有効です。
ふたば接骨院では、骨格のゆがみや神経の流れに着目し、頭痛の原因に直接アプローチする施術を行っています。
ただ痛みを取るだけでなく、再発しにくい身体づくりをサポートしています。
「整体で頭痛が良くなるの?」と疑問に思った方こそ、ぜひ一度ご相談ください。
あなたのその頭痛、身体からのサインかもしれません。
首や肩のコリが引き起こす緊張型頭痛
長時間のデスクワークやスマホ操作が続くと、首や肩の筋肉がガチガチに固まりやすくなります。すると筋肉の緊張によって血流が悪くなり、結果として脳に酸素や栄養が届きにくくなるのです。
このような状態が続くことで現れるのが、「緊張型頭痛」と呼ばれる症状です。
緊張型頭痛は、「締め付けられるような」「頭が重い」といった感覚が特徴で、慢性的に続くケースも少なくありません。
多くの方が痛み止めで対処していますが、それはあくまで一時的な緩和に過ぎず、根本的な改善にはなりません。
そこで注目したいのが整体によるアプローチです。
ふたば接骨院では、姿勢や骨格の歪み、インナーマッスルの弱化などに着目し、身体全体のバランスを整える施術を行っています。
整体によって筋肉の緊張を和らげ、血流を改善することで、頭痛の再発しにくい身体づくりを目指します。
「最近、頭痛が増えた気がする」「薬を飲み続けたくない」と感じている方は、ぜひ一度整体を体験してみてください。
あなたの不調の原因、実は身体の歪みにあるかもしれません。
薬でごまかす生活、もう終わりにしませんか?
頭痛薬は根本治療じゃない
市販の頭痛薬を飲むと、一時的に痛みが和らぎますよね。ですが、それはあくまで“対症療法”であり、頭痛の根本原因を取り除くものではありません。
それどころか、薬を飲む頻度が増えていくことで「薬物乱用頭痛(Medication Overuse Headache)」という、さらに厄介な慢性頭痛を引き起こすこともあるのです。
「薬が効かなくなってきた」「常に頭が重い」…そんな症状に悩んでいる方にこそ試していただきたいのが整体による根本改善です。
ふたば接骨院では、首や肩の筋肉の緊張、姿勢の崩れ、骨格のゆがみといった、頭痛の元になる要因を多角的にチェック。
一人ひとりの状態に合わせた整体施術で、身体全体のバランスを整えていきます。
また、当院が提供する「リバースボディ療法」では、骨盤や頸椎の矯正、神経伝達の調整、インナーマッスルの強化までをトータルでサポート。
こうした整体ケアを受けることで、薬に頼らず、頭痛の出にくい身体を手に入れることが可能です。
「もう薬には頼りたくない」そんなあなたへ――整体で頭痛のない毎日を目指しませんか?
「いつもと同じ頭痛」が慢性化する前に対策を
毎月のように頭痛に悩まされている方、それはすでに「慢性頭痛」の状態かもしれません。
「いつものことだから」と放っておくと、痛みがどんどん強くなり、生活に支障をきたす恐れもあります。
慢性頭痛の多くは、身体のゆがみや姿勢の悪さ、筋肉の緊張といった、見えない部分に原因があります。
特に首・肩周辺の筋肉が硬くなると、血流や神経の伝達がスムーズにいかなくなり、それが頭痛を引き起こす要因になります。
つまり、頭痛は“首からくる”ケースが非常に多いのです。
そうした状態を改善するには、身体のバランスを整えることが重要です。
ふたば接骨院の「リバースボディ療法」では、骨格の矯正・神経調整・インナーマッスルの強化といった多角的な整体アプローチで、頭痛の根本改善を目指します。
薬に頼らず、再発しにくい身体をつくるために、今こそ見直してほしいのが整体ケアです。
「薬が手放せない」「繰り返す頭痛にうんざりしている」そんな方は、一度しっかりと身体と向き合ってみませんか?
あなたのその頭痛、実は整体で変わるかもしれません。
整体でアプローチする“頭痛の本当の原因”
整体とは?ただのマッサージじゃない!
整体とは、筋肉・骨格・関節のバランスを整えることで、身体の不調を改善する手技療法です。
ただのマッサージとは違い、整体は“気持ちよさ”だけを目的とせず、根本原因にアプローチする点が大きな特徴です。
ふたば接骨院では、「肩こり」「腰痛」「頭痛」などの慢性的な症状に対して、ただ一時的に緩和させるのではなく、なぜその痛みが出ているのか、どこに原因があるのかを丁寧に検査・説明した上で施術を行います。
この“原因を突き止めて改善する整体”こそが、私たちのこだわりです。
また、当院の整体では、姿勢や骨盤の歪みだけでなく、神経の乱れやインナーマッスルの機能低下といった目に見えない部分にも注目。
「リバースボディ療法」という独自のアプローチで、身体を本来のバランスへと戻していきます。
「他の整体に行ったけど、すぐ戻ってしまった」「何が原因か分からないけど身体がつらい」そんな方にこそ、当院の整体を一度体験してほしいと考えています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの整体で、あなたの不調にしっかり寄り添います。
ふたば接骨院の整体で頭痛が軽くなる理由
当院で行っている「リバースボディ療法」は、背骨や骨盤の歪みを整えることで神経の流れや血流を正常化し、頭痛の根本原因にアプローチする施術です。
多くの頭痛は、首や肩の緊張からくる「緊張型頭痛」が多く、姿勢の悪化や筋肉の硬さが大きく関係しています。
特に注目すべきは、後頭部と骨盤のバランスです。
この2点がズレていると、首〜肩〜頭にかけての筋肉に無理な負担がかかり、慢性的な頭痛を引き起こす要因となります。
リバースボディ療法では、トムソンテクニックなどを用いて骨格を正しい位置に整えることで、「なんとなくいつも頭が重い…」という感覚がスッキリ軽くなるのを実感していただけます。
また、痛みの出ている箇所だけでなく、身体全体のバランスを診て施術を行うため、再発しにくいのも特徴です。
薬に頼らず、頭痛を改善したいと願う方にはぴったりの施術法です。
「もう薬は手放したい」「繰り返す頭痛にうんざり…」という方こそ、当院のリバースボディ療法でその頭痛から解放されてみませんか?
患者さまの声:整体で頭痛がラクになった!
「何年も頭痛薬を飲んでいましたが、ふたば接骨院に通ってから薬を飲む回数が激減しました!」
(豊橋市 40代女性)
「整体で頭痛が良くなるなんて半信半疑でしたが、今では体のバランスの大切さがよくわかります」
(豊川市 30代男性)
こうしたお声を多くいただくように、ふたば接骨院では頭痛の根本改善を目指した整体を提供しています。
一般的なマッサージでは表面的な筋肉しかアプローチできませんが、当院の整体は骨格・神経・筋肉のつながりを見極め、原因を深く追求します。
特に、姿勢の乱れや骨盤のゆがみが原因で起こる緊張型頭痛は、整体によって背骨や首の状態を整えることで改善が期待できます。
当院では、リバースボディ療法という独自の整体メソッドを導入しており、神経の興奮を抑え、血流の流れを正常化させるサポートを行います。
「長年の頭痛で悩んでいる」「薬に頼りたくない」そんな方には、ふたば接骨院の整体をぜひ一度体験してほしいと思っています。
信頼と実績に裏打ちされた整体で、あなたの生活をもっと快適にしませんか?
整体×生活習慣の見直しで再発防止!
あなたの姿勢、大丈夫?
猫背やストレートネックの姿勢は、首や肩に大きな負担をかけるため、頭痛を引き起こしやすいと言われています。
特に長時間のスマホ操作やデスクワークをしている方は、無意識のうちに首が前に出る姿勢になり、筋肉の緊張や血流の悪化が慢性化。これが頭痛の根本的な原因になっているケースが非常に多いんです。
こうした状態を改善するには、まず整体で身体のバランスを整えることが重要です。
ふたば接骨院では、骨格のゆがみを正すことで神経や血流の流れをスムーズにし、頭痛の出にくい身体づくりをサポートしています。
頭痛が改善されたあとも、正しい姿勢を維持することがとても大切です。せっかく整体で身体を整えても、姿勢が元に戻れば、頭痛も再発してしまうリスクがあります。
当院では、頭痛の原因を改善するだけでなく、再発防止のための姿勢指導やインナーマッスル強化のトレーニングも行っています。
慢性的な頭痛にお悩みの方は、薬に頼らず、整体を取り入れた根本改善を目指しませんか?
あなたの頭痛、姿勢を見直すことで変わるかもしれません。
インナーマッスルを鍛えて頭痛を予防
当院ではEMSを使った「インナーマッスルトレーニング」も実施しています。姿勢を保つための筋肉がしっかり働くことで、頭痛の予防につながります。
頭痛にお悩みの方は、今すぐご相談ください!
初回限定の整体体験も実施中
ふたば接骨院では、初めての方でも安心してご利用いただけるよう、【初回限定】のお得なクーポンをご用意しています。整体が初めての方でも、丁寧にカウンセリングを行い、身体の状態に合わせた施術をご提案します。
頭痛の原因が「姿勢」や「骨格の歪み」にあることは、意外と知られていません。整体で身体を整えることは、単なるリラクゼーションではなく、健康を根本から支える大切な選択肢の一つです。
頭痛薬に頼りたくない方、慢性頭痛に悩んでいる方は、ぜひ一度、ふたば接骨院の整体をお試しください。あなたの生活が“痛みのない快適な毎日”にリバースされるお手伝いをさせていただきます。
このような治療もしています
交通事故治療ご存知ですか?
ご予約方法はこちら
ありがたいお言葉頂きました

「大したことない」は危険!交通事故後に見落とされがちな体のサインとは?
交通事故は、ある日突然起こるもの。軽い接触やスピードの出ていない衝突でも、「少しぶつけただけだから平気」「痛みもないし、放っておけば治るだろう」と自己判断してしまう方が少なくありません。
しかし、実はこれが非常に危険なのです。
事故直後は興奮状態にあるため、痛みを感じにくいことも多く、数時間~数日経ってから首の痛み(むち打ち)、腰痛、頭痛、手足のしびれなどの症状が現れるケースがよくあります。これらを「気のせい」と思って放置すると、慢性化しやすく、最悪の場合後遺症が残る可能性もあるのです。
豊橋市南栄町にある【ふたば接骨院・鍼灸院】では、交通事故治療に特化した専門的な施術を行っており、「後遺症ゼロ」を目指したサポートを提供しています。お一人おひとりのお体の状態に合わせて、骨盤矯正・背骨矯正・最新電気治療機器を組み合わせたオーダーメイド施術を行っています。
この記事では、
-
交通事故後に起こりやすい代表的な症状
-
治療を受けずに放置することのリスク
-
なぜ“事故直後からの治療”が重要なのか
-
当院で行っている具体的な交通事故治療の内容
について、わかりやすく解説していきます。
「事故後からなんとなく体調がすぐれない」「病院では異常なしと言われたけれど、本当にこのままで大丈夫?」「そもそも、こういうときってどこに相談すればいいの?」——交通事故に遭った直後は気が動転していて気づかなくても、時間が経つにつれて、首の痛みや頭痛、めまい、倦怠感などがじわじわと出てくることがあります。特に「むち打ち症」などはレントゲンやMRIでは異常が見つからないことも多く、「原因不明」と言われてしまうケースも珍しくありません。
事故後の不調、放置していませんか?病院で異常なしと言われたあなたへ
「事故後からなんとなく体調がすぐれない」「病院では異常なしと言われたけれど、本当にこのままで大丈夫?」「そもそも、こういうときってどこに相談すればいいの?」——交通事故に遭った直後は気が動転していて気づかなくても、数日〜数週間たってから首の痛みや頭痛、めまい、吐き気、手足のしびれなどの症状が出てくることがあります。これは「むち打ち症(頚椎捻挫)」によく見られる特徴ですが、レントゲンやMRIなどの画像検査では異常が見つからないことも多く、「異常なし」と診断されてしまうことが少なくありません。
そんなときに頼りになるのが、交通事故治療の専門院です。豊橋市南栄町にある「ふたば接骨院・鍼灸院」では、交通事故によるケガや後遺症に特化した施術を行っており、国家資格を持つスタッフが医療機関と連携しながら対応しています。骨盤や背骨の歪みを整える矯正や、炎症を抑える電気治療、筋肉や神経の回復を促す鍼灸などを組み合わせて、あなたの身体に合わせたオーダーメイドの施術をご提供します。
事故後の不調や不安は、我慢するものではありません。早期に適切なケアを受けることで、後遺症のリスクを大きく減らすことができます。もし、少しでも「おかしいな」と感じたら、まずはふたば接骨院・鍼灸院までお気軽にご相談ください。その一歩が、健康な日常を取り戻すための第一歩になるはずです。
交通事故後の不調はすぐ相談を!放置は後遺症のリスク大
交通事故後に起こりやすい代表的な症状とは?
交通事故後の不調を放置するとどうなる?
-
慢性化のリスク
-
自律神経への影響
-
日常生活・仕事・家事への支障
-
後遺症として残ってしまう可能性も
なぜ交通事故直後からの治療が大切なのか?
-
初期対応の早さが症状改善の鍵
-
病院で異常がないと言われても油断しないこと
-
自賠責保険適用で治療費の自己負担は原則0円
-
交通事故専門院ならではのアドバイスと対応
ふたば接骨院・鍼灸院の交通事故治療の特徴
-
豊富な交通事故対応実績と専門知識
-
国家資格保有者による施術
-
骨盤矯正・背骨矯正で根本改善を目指す
-
最新電気治療器で痛みを深部からケア
-
病院や弁護士との連携もサポート
患者様の声・よくある質問
-
実際に通院された方の体験談
-
Q. 他の接骨院との違いは?
-
Q. どのタイミングで通院を始めればいい?
-
Q. 保険会社とのやり取りが不安…どうすれば?
まずはお気軽にご相談ください
-
相談・施術ともに交通事故患者様は自己負担0円
-
予約優先制で待ち時間も少なく通いやすい
-
豊橋市・南栄町近辺で交通事故に遭われた方へ
【第1章】交通事故後に起こりやすい症状と放置するリスク
交通事故で多い症状の特徴
交通事故の衝撃は、私たちの身体に想像以上のダメージを与えます。特に多いのは以下の症状です。
-
むち打ち(頸椎捻挫)
首が前後に大きくしなることで、筋肉・靭帯・神経にダメージが加わります。数日後から首の痛み、動かしにくさが現れることが多く、放置すると長引きやすいのが特徴です。
-
頭痛・めまい
むち打ち症状に伴い、首から頭への血流や神経伝達に支障が出ると、頭痛やめまい、吐き気が起こることがあります。
-
腰痛
事故の衝撃で腰に負担がかかり、筋肉の緊張や骨格の歪みが原因で腰痛が発生します。
-
手足のしびれ
首や腰の神経圧迫によるしびれ症状も多く、放置すると慢性化する恐れがあります。
-
自律神経症状(吐き気・倦怠感など)
身体のバランスが崩れ、自律神経が乱れることで、全身のだるさや吐き気、不眠などが現れることもあります。
症状を放置することで起こるリスク
「そのうち治るだろう」「痛みが軽いから大丈夫」と放置してしまうと、以下のリスクを招くことがあります。
-
慢性痛のリスク
初期段階での適切な施術が行われなければ、痛みが長期間続く「慢性痛」に移行する可能性があります。
-
関節や筋肉の柔軟性低下
事故による歪みをそのままにすると、関節の可動域が狭まり、筋肉の柔軟性も低下してしまいます。
-
自律神経失調の長期化
神経系のトラブルを放置すると、自律神経失調が長引き、心身の不調が慢性化するリスクがあります。
-
生活や仕事への影響
身体の不調が続くと、仕事や家事、趣味など日常生活全般に支障が出る可能性があります。
事故後すぐは痛みが出にくい理由と治療のタイミング
事故直後に痛みが少ない理由
早期治療の重要性
交通事故の症状は、早期に適切な治療を受けることで、後遺症を防ぐ可能性が格段に高まります。
事故後は、「痛みがない今のうちにこそ治療すべき」なのです。
ふたば接骨院・鍼灸院の交通事故専門施術の強み
交通事故専門の的確な評価と施術プラン
ふたば接骨院・鍼灸院では、交通事故による症状に特化した施術を行っています。
施術前には、以下を必ず実施します。
-
事故状況と衝撃の方向、強さの確認
-
症状の詳細なヒアリング
-
骨格・神経・筋肉のバランスチェック
これらの情報をもとに、一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイド施術計画を作成します。
多角的な施術で根本改善を目指す
ふたば接骨院・鍼灸院の強みは、施術メニューの豊富さと専門性の高さです。
-
骨盤矯正・背骨矯正
骨格の歪みを整えることで、身体全体のバランスを回復し、痛みの原因を根本から解消します。
-
鍼灸施術
神経や筋肉への直接アプローチで、痛みやしびれ、自律神経症状の緩和を図ります。
-
最新電気治療器
筋肉の深層部にアプローチすることで、血流を改善し、自然治癒力を高めます。
(※機器名は非公開のため、詳しくは直接お問い合わせください)
治療の流れと通院目安
当院の交通事故治療は、以下の流れで進行します。
-
初回カウンセリング・検査・施術スタート
-
施術の経過を確認しながら、内容を適宜調整
-
症状改善後は再発防止と生活指導を実施
通院頻度の目安は、
交通事故治療に関する具体的な疑問に答えます
Q1:自賠責保険は適用できますか?
→ はい、自賠責保険の適用が可能です。原則、治療費は0円で通院できます(※詳細は保険会社の対応によるため、個別にご確認ください)。
Q2:どれくらいの頻度で通院すればいいですか?
→ 症状の程度や個人差がありますが、事故直後は週2〜3回の通院が推奨されます。その後、症状の変化に合わせて調整していきます。
Q3:治療期間はどのくらいかかりますか?
→ 軽症の場合は1〜2ヶ月程度、むち打ちや神経症状が強い場合は数ヶ月以上かかるケースもあります。詳しくはカウンセリング時にご案内します。
Q4:病院との併用はできますか?
→ はい、整形外科など病院との併用は可能です。医師の診断を受けながら、接骨院での施術を同時進行する方も多くいらっしゃいます。
交通事故治療は“早さ”がすべて!迷わずご相談を
交通事故によるケガは、「軽いから大丈夫」「痛みがないから問題ない」と考えてしまいがちですが、それは大きな間違いです。
早期の正しい治療が、後遺症を防ぐ最大のカギです。
ふたば接骨院・鍼灸院では、
自賠責保険が使えるため、自己負担ゼロで施術可能なケースも多いです。
交通事故後の身体の不安は、放置せず今すぐご相談ください。
当院は交通事故(むちうち)治療を専門に行なっております。
交通事故治療(むち打ち治療)が得意な整骨院、豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院にさっそく電話してみる!
⇒①0120-555-411(フリーダイヤル)
②0532-46-4355
どちらでも繋がります!!
住所:豊橋市南栄町字空池8-104
スタッフ資格:術者は全員国家資格所持者
(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師)
TOPにもどる
アクセス・営業時間についてはこちら
交通事故の慰謝料はいくらもらえるの?
【その他】
豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院
むちうち症について
私たちにおまかせください

肩こりでこんなお悩みありませんか?
デスクワークが続くと、気づけば肩が重く感じる…そんなお悩みはありませんか?
肩こりがひどくなると、頭痛や吐き気を伴い、仕事や日常生活にまで影響を及ぼすこともあります。
つらい肩こりを和らげようと、マッサージを受けたり、湿布を貼ったり、市販の薬を使ってみたり…。その時は少し楽になっても、すぐに元通り。繰り返す肩こりに、うんざりしている方も多いのではないでしょうか。
「整体ってどうなんだろう?」「興味はあるけど、どこに行けばいいのか分からない…」とお悩みの方へ。
愛知県豊橋市南栄町にあるふたば接骨院・鍼灸院では、「肩こりの根本改善」を目的とした整体を提供しています。
「もう肩こりで悩まない」そんなあなたの想いに、私たちは本気で応えます
肩こりに悩まされる毎日から解放されたい──そんな願いをお持ちの方へ。
ふたば接骨院では、単なる“その場しのぎ”の施術ではなく、肩こりの原因となる骨格の歪みや筋肉のアンバランス、神経の働きまでを整えることで、根本的な改善を目指します。
よくあるマッサージでは「気持ち良い」と感じても、時間が経てば元に戻ってしまうケースが多いものです。
私たちはそこに留まらず、再発しにくく、根本から健康を取り戻すための施術を提供しています。
一人ひとりの身体の状態に合わせて、「リバースボディ療法」をはじめとした丁寧な検査・施術・アフターケアを行い、本来あるべき正しい身体のバランスへと導いていきます。
「もう肩こりで悩みたくない」
「毎日をもっと快適に過ごしたい」
肩こりのつらさに、もう終止符を――ふたば接骨院があなたをサポートします
「この肩こり、ずっと付き合っていくしかないのかな…」
そんなふうに感じながらも、日々の忙しさに追われ、つらさを我慢してはいませんか?
私たちふたば接骨院・鍼灸院は、そんなあなたの“もう肩こりで悩みたくない”という想いに、本気で向き合います。
一時的な気持ちよさではなく、再発を防ぎ、健康な状態を維持できる身体づくりを目指して、骨格・神経・筋肉に総合的にアプローチする「リバースボディ療法」を行っています。
肩こりは、放っておいてよくなるものではありません。
そして、マッサージや湿布でごまかし続けるだけでは、いつまでたっても根本的な改善にはつながらないのです。
だからこそ今こそ、「変わるきっかけ」を一緒に見つけてみませんか?
これまで我慢してきた肩のつらさ、もう卒業しませんか?
あなたが本来持っている自然なバランスと元気を取り戻すために、私たちが全力でサポートいたします。
📍 愛知県豊橋市南栄町にある「ふたば接骨院・鍼灸院」で、
🌿 心と身体がホッとする時間をご提供いたします。
あなたのご来院を、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
なぜ肩こりは繰り返すのか?その根本原因とは
姿勢の悪さが肩こりを引き起こすメカニズム
「肩こりの原因は、筋肉が硬くなり血流が悪くなること」──そう聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
確かにそれも一因ではありますが、実はその背景にはもっと深い原因が潜んでいます。
それが「骨格の歪み」や「姿勢の崩れ」です。
たとえば、長時間スマートフォンを操作したり、パソコン作業をしていると、無意識のうちに頭が前に出た姿勢になります。
この状態が続くと「ストレートネック」や「巻き肩」になりやすく、首や肩の筋肉に常に負担がかかった状態に。
やがてその負担が蓄積し、筋肉が硬くなることで血流が悪化し、慢性的な肩こりへとつながっていくのです。
さらに、骨格が歪むことで身体全体のバランスも崩れ、肩まわりだけでなく、背中や腰、場合によっては脚にまで影響を及ぼすこともあります。
つまり、肩こりは単なる「肩の問題」ではなく、全身のバランスの乱れによって引き起こされる症状とも言えるのです。
だからこそ、肩こりを本当に改善したいなら、筋肉だけでなく骨格や姿勢に着目した根本的なケアが必要です。
現代人の生活習慣が筋肉と骨格を歪ませる
日々の暮らしの中で、何気なく行っている習慣が、実は肩こりの大きな原因となっていることをご存じでしょうか?
たとえば、スマートフォンを長時間見続ける、猫背になったままでデスクワークをする、食事中や仕事中に肘をついてしまう、あるいは重いカバンをいつも同じ肩にかけている──。これらはすべて、現代人に多く見られる生活習慣です。
一つ一つは小さな癖のように思えるかもしれませんが、これらの動作は、知らず知らずのうちに身体へと負担をかけています。
特に首・肩・背中まわりの筋肉は、常に緊張を強いられ、徐々に柔軟性を失っていきます。
その結果、筋肉が硬くなり、血流が悪くなり、肩こりとして表れてくるのです。
さらに、こうした姿勢のクセが積み重なると、身体のバランスそのものが崩れ、骨格に歪みが生じてしまいます。
そしてこの骨格の歪みこそが、慢性的な肩こりを引き起こす“根本的な原因”なのです。
つまり、肩こりを本気で改善するためには、単に筋肉をほぐすだけでは足りません。
毎日の姿勢や身体の使い方、そして歪んでしまった骨格そのものを整えるケアが必要なのです。
放置してはいけない肩こりのリスク
「肩こりくらいで整体に行くなんて、ちょっと大げさかな…」
そんなふうに感じて、つらさを我慢していませんか?
実はその“がまん”が、将来的に思わぬ身体の不調につながってしまうかもしれません。
慢性的な肩こりは、単なる疲れやコリではなく、身体からの「不調のサイン」。
放っておくことで、さまざまな症状を引き起こすリスクがあるのです。
たとえば、肩の筋肉が緊張し続けることで血流が悪化し、頭痛やめまい、吐き気といった症状を感じる方も少なくありません。
また、首や肩まわりには自律神経が通っているため、自律神経が乱れ、不眠や不安感を引き起こすケースもあります。
さらに、肩関節の動きが悪くなると五十肩(肩関節周囲炎)を発症したり、神経を圧迫して腕や手にしびれ、神経痛が現れることもあります。
そして姿勢の悪化が進むと、バランスの崩れから腰痛や膝痛へと広がることさえあるのです。
こうした悪循環を防ぐためにも、「まだ大丈夫」と放置せず、早めにケアを始めることが大切です。
整体は、肩こりの症状が軽いうちにこそ受けていただきたい施術です。
ご自身の身体を守るために、まずは小さな不調のうちから対処していきましょう。
ふたば接骨院の整体で肩こり改善!「リバースボディ療法」とは?
ふたば接骨院では、肩こりの根本改善に特化した**「リバースボディ療法」**を導入しています。
これは単なるマッサージではなく、骨格・神経・筋肉・インナーマッスルの4つのポイントに総合的にアプローチする施術法です。
Point① 骨格矯正で正しい姿勢へ
Point② 神経の調整で痛みの元をブロック
Point③ 筋肉と関節の修復
-
手技療法や電気治療、場合によっては鍼を使用
-
硬くなった筋肉をゆるめ、関節の可動域を広げる
-
施術後には「肩が軽くなった」と多くの方が実感!
Point④ インナーマッスルの強化
これらを組み合わせたオーダーメイドの整体施術で、あなたの肩こりをしっかり根本から改善していきます。
施術を受けた方の声と変化
ふたば接骨院では、肩こりでお悩みだった多くの方が、施術を通して「本当に楽になった!」と実感されています。
その中でも特に評価されているのが、**単なるマッサージや一時的な緩和ではなく、肩こりの根本にアプローチする「リバースボディ療法」**です。
実際にご来院された方から、こんなお声をいただいています。
「デスクワークでいつも肩がパンパンで重たかったのですが、数回の施術で本当に軽くなり驚きました。
姿勢も自然と良くなり、自分に自信が持てるようになった気がします。」(30代・女性)
「他の整骨院にも行ったことがありますが、痛みが戻ってしまって続きませんでした。
ふたば接骨院は説明が丁寧で納得できるし、何より効果を実感できました。」(40代・男性)
ふたば接骨院が大切にしているのは、「その場しのぎの気持ちよさ」ではありません。
身体の状態を丁寧に見極めながら、骨格・筋肉・神経・インナーマッスルまでトータルで整え、再発しにくい健康な身体をつくることを目指しています。
だからこそ、一度楽になった症状が戻ってしまう前に、しっかりとケアを継続することで、「肩こり知らずの身体」へと導くことができるのです。
あなたも、そんな変化を体感してみませんか?
今こそ、肩こりの悩みから解放されましょう!
つらい肩こり、我慢し続けていませんか?
整体の力で、あなたの身体はもっと楽になります。
私たちふたば接骨院では、あなたが安心して施術を受けられるよう、丁寧なカウンセリングと施術計画をご提案しています。
ご予約・お問い合わせはこちら
📍 ふたば接骨院・鍼灸院
📍 愛知県豊橋市南栄町字空池28-10
📞 TEL:0532-47-5580
🌐 公式サイトはこちら
初回限定キャンペーンのご案内
今なら、初回限定でリバースボディ療法が3,980円(税込)で体験できます!
通常価格8,800円(税込)→ 初回限定価格3,980円(税込)
「整体で肩こりをどうにかしたい」と思った今がチャンスです!
まとめ
-
肩こりは放置すると全身に悪影響を及ぼすリスクがあります
-
骨格・神経・筋肉にアプローチする整体「リバースボディ療法」で根本改善を目指せます
-
豊橋市南栄町で整体をお探しなら、ふたば接骨院へお気軽にご相談ください
このようにお身体を診させていただきます!
嬉しいお言葉を頂きました
ご予約方法はこちら
交通事故に遭ってしまったら、、、
手順を豊橋市ふたば接骨院を徹底解説!!

1. まずは警察へ通報し、事故証明を取得する
発生したら、まず何よりも警察に通報することが最優先です。
たとえ相手が「お互いにケガもないし、示談で済ませましょう」と言ってきたとしても、絶対にその場で示談しないようにしましょう
警察に連絡をすると、現場の状況確認が行われ、「交通事故証明書」が発行されます。この証明書は、後に自賠責保険や任意保険を使って治療費や慰謝料の請求を
するために必要不可欠な書類です。また、事故当日はアドレナリンが分泌されており、痛みを感じにくい状態になっていることも多く、ケガに気づきにくいもの
です。そのため「痛くないから大丈夫」と思って通報しなかったことが、後々大きな後悔につながるケースもあります
ふたば接骨院に来られる患者さんの中にも、「最初は軽く考えていたけど、数日後に首や腰が痛くなってきた」とおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
小さな事故でも必ず警察へ連絡しましょう。
2. 相手の連絡先・保険情報・現場状況を記録する
事故現場では、混乱していても冷静に記録を取ることが重要です。後々の保険対応やトラブル防止のためにも、以下の情報は必ず押さえておきましょう。
スマートフォンで撮影しておけば、後から客観的な証拠として役立ちます。特に、「どちらに過失があるか」「どの方向から衝突したのか」といったことは、
事故状況の写真があることで説得力を持ちます。
また、相手が保険に未加入だったり、連絡が取れなくなるケースもゼロではありません。そのため、その場で必ず連絡先と保険会社の確認を行いましょう。
ふたば接骨院では、こうした記録の取り方のアドバイスも行っています。事故直後に不安な方は、お気軽にお電話ください。
3. 必ず病院や整形外科で医師の診断を受ける
「痛みはないし、病院に行かなくていいか」と自己判断してしまう方が少なくありません。
しかし、交通事故によるケガ、特にむち打ち症や腰の捻挫は、時間が経ってから症状が出るケースが非常に多いのです。
そのため、事故当日か遅くとも翌日には、病院(整形外科)で診察を受けることをおすすめします。
ここで医師に診断してもらい、「診断書」を発行してもらうことが大切です。これがないと、自賠責保険での接骨院通院に支障が出てしまうことがあります。
レントゲンやMRIでは骨折や異常がないと判断されても、実際には筋肉や靭帯、神経がダメージを受けていることもあります。
これは画像診断だけでは分かりづらいため、整形外科と併せて、専門的な手技が得意な接骨院でのケアが非常に有効です。
ふたば接骨院では、医師の診断書をもとに保険適用での通院が可能です。まずは病院で検査を受けた後、ご来院ください。
4. 接骨院に通院する際の正しい流れ
接骨院への通院は、基本的に**医師の許可(診断書)**があれば、自賠責保険の適用で治療費が自己負担なく受けられます。
しかし、保険会社に対して「どこの医療機関に通うか」は事前に伝える必要があります。
通院の流れとしては、以下のようになります:
-
事故発生後、警察に届け出
-
病院で診断を受け、診断書をもらう
-
保険会社に「ふたば接骨院に通いたい」と伝える
-
接骨院で治療スタート
保険会社によっては、整形外科以外の通院を渋る場合もありますが、患者には医療機関を選ぶ権利があります。
お困りの際は豊橋市ふたば接骨院へご相談ください!
5. 保険会社とのやり取りの注意点
交通事故に遭った際は、」加害者側の保険会社と連絡を取る必要が出てきます。ここでのやり取りがスムーズにいかないと、
通院の開始が遅れたり、補償に関するトラブルが
生じる可能性があります。保険会社から連絡があったら、まず以下の情報を伝えましょう:
-
診察を受けた病院名
-
診断書の内容(例:頸椎捻挫)
-
通院希望先として「ふたば接骨院」と明示
時折、「接骨院ではなく病院で」と言われることもありますが、これはあくまで提案です。患者本人が希望すれば、接骨院での通院も保険の対象になります。
ふたば接骨院では、保険会社との連絡サポートや、必要に応じた報告書の作成も行っております。慣れない手続きでお困りの方も、安心してご相談ください。
6. 後遺症を防ぐために必要なこと
交通事故の怖さは、「すぐ痛くない」ことにあります。むち打ちや腰の痛みは、数日~数週間たってから現れることが多く、放置してしまうと慢性化・後遺症とし
て残るリスクがあります。当院に通われている患者さんの中にも、「もっと早く来ていれば良かった…」と後悔される方がいらっしゃいます。
事故後の体は、見えないダメージを受けている可能性があるため、早めの検査・治療開始が鍵です。
ふたば接骨院では、交通事故専門の施術メニューを用意しており、
-
骨盤矯正
-
背骨矯正
-
ハイボルテージ電気治療
-
鍼灸治療
など、患者さまの状態に応じたオーダーメイド施術を行っています。
国家資格者が在籍し、丁寧なカウンセリングと計画的な通院プログラムで、後遺症ゼロを目指します。
最後に、、、
交通事故後は、落ち着いて正しい手順を踏むことが、心身の回復と保険トラブル回避のために非常に大切です。
もし事故に遭ってしまったら、
✅ 警察に通報
✅ 情報の記録
✅ 病院で診断
✅ 接骨院で施術開始
という流れを思い出してください。
豊橋市南栄町のふたば接骨院・鍼灸院では、交通事故後の患者様を**「施術だけでなく手続き面までトータルサポート」**いたします。
些細なことでもお気軽にご相談ください。
トップページへ戻る